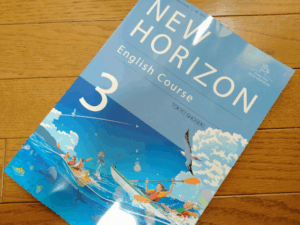第38回 中3ユニット6:P77- P87『ニューホライズン3』単語, 文法ガイド
『New Horizon』シリーズ目次
旧2021令和3年度版(2ページ目)

(DEEY─)後置修飾の山を越えて中学の文法はこのユニットで最後。
中学教科書『ニューホライズン(東京書籍)』の 単語・熟語・文法解説シリーズ。
『New Horizon 3 』として実質最終回の第38回は、
・ユニット6
・77ページから87ページ
まで、文法の締め[仮定法]を解説します。
前書き、使い方
新単語は以下のような”凡例(ルール)”にしたがって記述しています。
─ 凡例 ─
word(s):<品詞> 「和訳」 。〜説明〜
phrase:<句>「和訳」。〜説明〜
英語は同じ綴りで<動詞>で使ったり<形容詞>で使われたりします。そのためここでは”どの<品詞>”で使われているかも併記します。
“<名詞>として(使われている)。”
と書かれていた場合は、その単語はいくつかの品詞の種類があるけれど、本文では<名詞>として使われていることを示します。
“<名詞>”
とだけ書かれている場合は、その単語はほとんどの場合<名詞>以外の用法はないことを示します。
ラッキー。
『ニューホライズン 3』
─ 2025年度版 目次 ─
p.77
Unit.6 – What does it mean to be a global citizen?
p.80
Unit.6 – Read and Think 1
p.84
Unit.6 – Unit Activity
Grammar 4 – 仮定法
p.87
Unit.6 – What does it mean to be a global citizen?
p.77
中学英語文法もこれで最後。
「文法、高校であとどれくらい残ってるの?」
もうほとんど残ってない。英語文法の8割は中学で終っていて、残りは中学で説明しきれなかった部分くらい。
・過去完了(現在完了はやった)
・完了形の受動態
・進行形の受動態
・分詞構文
・直接話法・間接話法
・仮定法過去完了
など残っているのは、これまでやったことの応用がほとんど。
それでは最後の[仮定法]、「もし〜だったら」を英語でどう表現するか?を見ていこう。
p.78
– Part 1 /
国際協力のキャンペーン広告
[仮定法: I wish … ]
[KS-19] I wish I could …
I wish I had …
願いや願望を表す動詞に wish がある。日本語では「〜を願う、望む」という意味だが目的語はさまざま。
1)wish + 名詞
「〜を望む」
2)wish + to 不定詞(名詞用法)
「〜であることを願う」
3)wish + 節
「〜であればよかったと思う」
特に3) のかたちで使う場合、「(節)だったらなあ」という現実には起きなかった願望を表せる。
「映画見に行けたらよかったのに」
・I wish I could go out and watch some movies.
このとき(節)は過去形にする。でもこれは日本語も同じだ。「〜だった(過去形)ら」と表現している。
campaign:<名詞> 「キャンペーン」。
ある目的を達成するための組織的な手段や手順や運営。
ちなみに、このような組織的な運営行動は、選挙”活動”や企業”経営”など動詞は “run” を使うことが多い。
run a company
「会社を運営する」
run for president
「大統領に立候補する」
などなど。
backpack(s):<名詞>として、「バックパック、リュック」
overseas:<副詞>「海外に(へ)」。
一般的には海を渡った外国のこと。
this way:<名詞句> 「この様」「こんな風」。
会話ではよく出てくる。
feel this way
「このように感じる」
feel that way
「そのように感じる」
felt that way
「そのように感じた」
“this”と”that”では心理的な距離感が違う。昔のことや何か他人が言ったことを思い出しながら言うなら”that”を使いたい。
unused:<形容詞> 「使われていない」。
un + use + ed で「否定」+「使う」+ ed。
abroad:<副詞>「外国に(へ)」。
こっちは陸続きを含む外国のイメージ。overseas は海を渡って遥かな遠い国のイメージ。
supply, supplies:<名詞>として「支給されたもの」
donate:<動詞> 「寄付をする」
p.79
– Part 2 /
海を渡るランドセルの話
[仮定法:If + S + were … ]
[KS-20] If I were … , I would …
パート2では、if を使った仮定法「もし〜であれば、ーだろうに。」という表現。
この文の後半節の「ーだろうに」は wish の時と同じで、今度は前半が
「もし〜なら」
という条件節になるパターン。
「もし学生じゃなかったら、平日にその映画見れたのに」
・If I weren’t a student, I could watch the movie on weekdays.
このとき両方の節を過去形にするのが英語のルール。前半の[if節]も過去形にする。
それと比較して日本語は微妙
「もし学生じゃなかったら」
「もし学生じゃないなら」
あまり区別はしない感じ。
以上は実現しなかった事柄を表し、過去形で表現するので[仮定法過去]なんて言い方をする。
groups that collect …:「グループ/〜を集めている」。groups と複数形だが、続く(主格)関係代名詞は those でなくてよい。
ただし動詞は groups に合わせる。例えば単数の group だったなら group that collects になる。
so far:<慣用句><副詞句> 「今のところ」。
“far”は「遠い」の意味から「(それなりの)範囲」という意味でも使う。教科書では文頭にあるが、文末に置いてもいい。
more than 260,000 backpackers:「より多く/26万のカバン」。
ここでは more は代名詞である。More have been sent. というのが文の骨格。
If …, I would do …:「もし〜なら、〜しただろうに」。
仮定法過去の後半節に would を使うのは、will が意思を含むから。「もし〜なら、〜出来ただろうに」と言いたい時は could が使える。
Actually:<副詞>「実際は、本当は」
definitely:<副詞>「必ず、ぜったい」「間違いない」。
発音とアクセント位置注意。/ デフィニトリ/
Unit.6 – Read and Think 1
p.80
先に83ページの文法解説を読んでから、リードアンドシンクに進もう。
引き続き仮定法と、あと関係代名詞の応用の話をひとつする。
life without school:「人生/学校なしの」。<前置詞句> without school が life を後置修飾している。
children living like this:「子供たち/暮らしている/このように」。living は現在分詞で children を後置修飾している。
children like these …:「子供たち/このような」。like these 以下が children を後置修飾している。Children から Afghanistan までが主語。
Most of … come with …「ほとんど/〜の/来る/〜と一緒に」。主語は無生物の most 。「カバンのほとんどはペンとノートと一緒に来る」
in these way:「このような方法で、具合で」
from one A to another (A):<慣用句> 「1つのAからその他の(A)まで」。ひとつのAから別のAの同種類へ、数珠つなぎに現象が起きている感じ。
本文では、”A”は”contry”で、また”another”の後ろの”country”は繰り返しになるので省略する。
only lines on a map:<句>「ただの線/地図上の」。ここの文脈では “only” ではなく “just” のほうがいいと思われる。
“only” の<形容詞>は量的数的に「たったの」「唯一の」というニュアンスであって、「単なる」ではないと思う。
「線画アート」であれば “artwork with only lines” でいいだろう。「線だけで描かれた絵」
先生に聞いてみて欲しい。
Unit.6 – Read and Think 2
p.82
for its survival:「日本の生き残りのために」。for は目的「〜のため」のイメージ。
to 不定詞の副詞用法が目的で使える。つまり to survive と言い換えてもいい。
Many things that we see …:「たくさんのもの/私たちが見かける」。83ページの解説参照。
one-third:「1/3」
such as …:「例えば」
for example …:「例えば」
like …:「例えば」。「例えば」三連発。同じ言い回しをしたくないので表現を変えている。
for example の後ろは節が来ることが多い。他は名詞が来る。
many products that are … are made …:ここも83ページの関係代名詞のせいで主語がでかいパターン。
骨格は
many products are made in other countries.
are no exception :「例外がない」。are not exception 「例外ではない」。何か違う?
Unit.6 – Read and Think 2
p.82
p.83
– Read and Think 2 /
[仮定法(If + S + 動詞過去形)]
[KS-21] If … had …, I would …
[主語を後置修飾する関係代名詞]
[KS-22] things that … come …
KS-21は引き続き仮定法のはなし。
KS-20では「もし私だったら」「もし〜なら」とif節は be動詞 were のパターンだった。
もちろん一般動詞のパターンもありで、その時はやっぱり過去形にする、と言うはなし。
「お腹痛くなければ映画に間に合ったのに」
・If I didn’t have a stomach ache, I could make it to the movie on time.
ここまでが仮定法の話しで、KS-22は再び関係代代名詞の話にもどる。例文─
「多くの洋画はアメリカ製だ」
・Many foreign films that we can watch in Japan come from the U.S.
これはSVO型の文型。
「ではどこまでがS?」
答えは Manyからin Japanまで。
「…長いな…」
でもこのような文章は比較的目にする。この文の骨格は
Many films come from the U.S.
でこれを書いた人は、
Many films …
と書き始めた時に「日本で見ることのできる」という情報を付け足したくなったのだ。
そこで関係代名詞を使って many films の後ろにこの情報を付加(後置修飾)した。
結果でっかい(長い)主語になった。
英語はこう考えるとけっこう便利。どんどん情報を付け足していける。
日本語はそうはいかない。
「多くの映画は…」
「あ、私たちが見てる、あ、日本でね、はね、」
とカタコトになってしまう。
Unit.6 – Unit Activity
p.84
地球市民としての抱負を伝える
Real Life English(Listening)
P.85
テレビの国際ニュース
Learning Social Studies in English
P.86
テレビの国際ニュース
Grammar 4 – 仮定法
P.87
>>> 仮定法 〜現実とは異なる願いや条件〜
以上、第38回『ニューホライズン 3』ユニット6
関連図書:

ワーク&テスト ニューホライズン 3年
引用元:

東京書籍 令和7年4月新刊 中学教科書 NEW HORIZON English Course 3 [教番:英語002-92]
東京書籍 発行