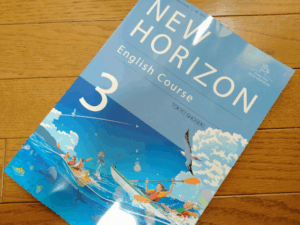第36回 中3ユニット5:P61- P71『 ニューホライズン3』単語, 文法ガイド
『New Horizon』シリーズ目次
旧2021令和3年度版(2ページ目)

(DEEY─)受験のためにも、できれば教科書は夏休みまでには終わらせたい。
中学教科書『ニューホライズン(東京書籍)』の 単語・用語解説シリーズ。
今回は文法として最重要な関係代名詞と後置修飾が登場する第36回。『New Horizon 3 』
・ユニット5
・61ページから71ページまで
を解説します。単語も連語も。
前書き、使い方
新単語は以下のような”凡例(ルール)”にしたがって記述しています。
─ 凡例 ─
word(s):<品詞> 「和訳」 。〜説明〜
phrase:<句>「和訳」。〜説明〜
英語は同じ綴りで<動詞>で使ったり<形容詞>で使われたりします。そのためここでは”どの<品詞>”で使われているかも併記します。
“<名詞>として(使われている)。”
と書かれていた場合は、その単語はいくつかの品詞の種類があるけれど、本文では<名詞>として使われていることを示します。
“<名詞>”
とだけ書かれている場合は、その単語はほとんどの場合<名詞>以外の用法はないことを示します。
ラッキー。
『ニューホライズン 3』
─ 2025年版 目次 ─
p.61
Unit.5 – What makes a good leader?
p.68
Unit.5 – Unit Activity
Grammar 3 – 後置修飾
p.71
Unit.5 – What makes a good leader?
p.61
ユニット5はいよいよ関係代名詞。そして後置修飾の説明。
この後置修飾はとても大事な英語のシステム。
とはいってもさらに新しいことを覚えると言うよりは、
「これまでやってきたこんなことあんなこと、整理すれば全部後置修飾ですよね?」
という確認。
p.62
– Part 1 /
ガンディーについて紹介
[名詞を後ろから修飾する文]
[KS-15] a picture I found
パート1でまず名詞を修飾する方法について改めて考える。
ユニット4でやった過去分詞・現在分詞を思い出すと、
・the movie called ”the Best Movie of this year”
・the movie playing at the theater
これらの形容詞句も名詞を後ろから修飾していた。(句とは主語・動詞が共には含まれな文の一部を言う)
今回は名詞の後ろに形容詞節(主語・動詞を両方含む)を用いて修飾しようと言うもの。
the move I watched (a movie)
直訳「映画/私が見た」
意訳「私が見た映画」
<形容詞節>が後ろから名詞を修飾している。
internet:<名詞>「インターネット」
on the internet :「インターネットで」on を使う。
person:<名詞> 「(特定の)個人」。
複数形は文脈によるが、”persons”「その特定の個人の集まり」。
“people”は、特定された個人ではない「一般の人々」というイメージ。
Gandhi:<人名> 「ガンディー」。
”Mahatma Gandhi”として欧米圏でも名が知られている人物。覚えておいて損はない。
image:<名詞>「画像」「イメージ像」
print(ed):<動詞>「印刷する」
rupee notes:<名詞> インドの「ルピー紙幣」。
“note”<名詞><英>は”banknote”の省略形で、「中央銀行が発行した紙幣」で、要は「お札」のこと。
特にイギリスで使われる言い方。アメリカでは”bill”を使うのが一般的。
leader:<名詞>「指導者、リーダー」
greatly:<副詞>「大変、大いに」
a leader people respect greatly:「リーダー/人々が/尊敬する/大いに」。leader を後ろから節が説明修飾している。
born:<形容詞><過去分詞> 「生まれる」。
Be動詞とともに受け身形で使う。もとは”bear”<動詞>「(ものを)運ぶ」の<過去分詞>の形。
national:<形容詞>「国の」「国民の」。
non-violence:<名詞> 政治や社会的問題に対して「非暴力(主義)」。
p.63
– Part 2 /
ガンディーについて話す
[関係代名詞 who]
[KS-16] a man who has …
名詞を後ろから修飾するシリーズ。ここから関係代名詞という用語を使い始める。
まずは例文
1) my friends viewing the movie
2) my friends who are viewing the movie
上の二つは共に「微笑んでいる女性」と同じことを言っている。
1)が現在分詞を使った表現。
2)がここで学ぶ関係代名詞 who を使った表現。
で 2)は次のようなことなのだ。
my friends (friends) are viewing
who は代名詞なので my friends = who なのだ。
関係代名詞わからなくなったら、直前の名詞に置き換えて読んでみる。
ちなみにここでは who はこの節の主語になっていので、
「主格の関係代名詞 who」
とか
「関係代名詞 who の主格用法」
とか言っている。
independence:<名詞> 「独立した状態」。/インディ-ペンデンス/。
violence:<名詞> 「暴力」。
fight:<動詞> 「戦う」。
不規則動詞で<過去形><過去分詞>ともに”fought”と変化する。よく見るので覚えよう。過去形の発音は/フォート/。
「〜のために戦う」という使い方が多く、前置詞”for”とともに使う。
human rights:<名詞> 「人間の諸権利」=>「人権」。
人には様々な権利があるので、複数形で使う。
go on:<句動詞> ここでは「取り掛かる」「始める」の意味と、「続ける」の意味の両方が合わさったイメージ。
“on”の「上に乗せる」イメージと、「すでに乗っかっている」イメージとで”go on”の意味にバリエーションが与えられる。
fast(s):<名詞> として、ここでは「断食(だんじき)」。
「速い」の”fast”とスペルは同じ。
protest:<動詞> 「抗議する」。
/プロテスト/。アクセントの位置に注意。”to protest”は<to不定詞>の副詞的用法。「抗議のために」
tough:<形容詞> (どうにか耐えられるだろうけど)「厳しい」
That sounds …:「〜に響く/聞こえる)」=>「〜(な感じ)ですね」。
五感系の表現はいろいろ。この場面では”It looks tough.”とは言わないだろう。見てはいないし。
では、”seems”はどうだろう?「〜みたいですね」これは使える気がする。
見(see)てはいないが、聞いた発言から想像して自分の頭にイメージして「〜のようですね」。
Unit.5 – Read and Think 1
p.64, p.65
– Read and ThinK 1 /
ガンディーの伝記
リードアンドシンクも引き続き関係代名詞。名詞が人の時 who を使った。
「じゃあ、人じゃない時は?」
which か that を使う。
「名詞なら目的語としても使うパターンとかあったりする?」
します。解説は67ページで。
前のユニットでもそうであったように、今回も先に67ページのKey Sentence と解説を先に読んでおく。
(ここは”NewWords”に和訳が付いていますので、本文の解説を中心にします。)
it was under British rule:「イギリスのルールの下だった。」「イギリスの支配下だった」
at that time:<副詞句> 「その当時は」「その時は」。
長い時間幅があるイメージ。昔話などもこちらの表現。
“at the time”は「その時」。短い時間で最近の出来事を語る時のイメージ。この前の出来事など。
“at a time”だと「一度に」という別の意味に。
Indian:<固有名詞>「インド人」「インドの」。
「アメリカ先住民」を意味することもあるので時として紛らわしい。
made a law that (=a law) was even more unfair …“:「つくった/法律を/それは/さらにより/不公平」。先行名詞が a law で、関係代名詞 that の主格用法。
<関係代名詞>が主語となる場合は、省略しない。目的語になる場合は省略できる。
stand up:<句動詞> 文字通り「立ち上がる」。
その後に前置詞が続くと意味が以下のように派生する。
“stand up against …”「〜対して立ち向かう」
“stand up to …”「〜に対して立ち向かう」
日本語では同じ意味になるが前置詞のもつイメージに引っ張られる。
“against”は法律(本文の”the law”)や物事などに対して。”to”は人に対して。
“stand up to the bully” 「そのいじめっ子に立ち向かう」
even if:<副詞句> 「たとえ〜だとしても」。
evenはifを強調している。この辺りは日本語の感覚に近い。”if”「もし〜なら」とは違う感覚。
Gandhi himself:「ガンジー彼自身も」
the law was removed:「その法律は取り除かれた」。「その法律はなくなった(廃止された)」
p.65
in those days:<副詞句> 「そのころは」。
上に出てくる”at that time”と何が違うのか?これも日本語の感覚に近い。
日本語で「あの当時は」と「その頃は」とは何が違うのか?
ほぼ同じ意味だ。だけど言い回しを変えたいのだ。
特に英語ネイティブは、同じ単語や用語(名詞は除く)を連続して使いたくない人たちである。
a law that (=a law) British made for salt:「ある法律/イギリスがつくった/塩(の取引)のために」。
<関係代名詞>の”that”は British made (a low = that) の目的語になっているので省略もできる。ここでは省略していない。
according to …:<副詞句>「〜によれば」。
put tax on …:<句>「〜に税を置く」「〜に課税する」
thousands of:<句><口語> 「何千もの〜」「多くの〜」。
1,000を複数形にして表現する。数としては、頑張れば数えられるくらい。
“tens of thousands of …” や “millions of …” になると数えられないほどの大量な数の表現になる。
legacy:<名詞> もともとは「相続遺産」という意味。
そこから派生して、「後世代に受け継がれるべき”物”や”出来事”、あるいは人物の功績」「レガシー」。
the legacy that Gandhi left:「功績/ガンジーが/残した」
Unit.5 – Read and Think 2
p.66
discrimination:<名詞>「差別」。
人種、肌の色、出身地、宗教、年齢、性別、身体、すべての差別に使う。発音は、/ディスクリミネーション/。
independence:<名詞>「独立」。
特に権力に制限されていない自由な状態。発音は、/インデペンデンス/。
dependence は反対の意味になって、「依存」とか「従属」となる。
non-violence:<名詞>「非暴力」。
特に政治的・社会的な変化を力を使わずに起こすこと。
p.67
– Read and Think 2 /
[関係代名詞 that/which(主格)]
[KS-17] a movie that (which) makes …
[関係代名詞 that/which(目的格)]
[KS-18] a move that (which) I watched …
関係代名詞。先行する名詞が人の時は who だった。
で先行詞が人以外の時は that か which を使う。
「どう使い分けるの?」
基本どちらでもいい。イギリス人は which、アメリカ人は that を使う場面が多いと思う。ただしthat しか使わないパターンがある。
the move that (which) makes her famous.(主格)
直訳:「映画/それは/つくった/彼女を/有名に」
意訳:「彼女を有名にした映画」
これがKS-17。
ところで(関係代)名詞だとしたら、目的語で使われることもあるだろう。
これはすでにやっている。見た記憶があると思う。
the move I watched yesterday
「映画/私が/見た/昨日」
この節の the movie は、後ろに続く I watched yesterday には欠けている目的語だ。
この節の本来の完全形は
the move that (which) I watched yesterday(目的格)
なのだ。これを「関係代名詞の目的格」とか言う。そしてこの目的格として that / which / who を使う時これらは
省略してもよい
それが[KS-15]のかたち
the movie I watched yesterday
Unit.5 – Unit Activity
p.68
理想のリーダーを紹介しよう
─ 人が目的語となる関係代名詞 ─
STEP2の例文中に次の一文。
The person I respect is Gandhi.
先行名詞が人(The person)でこの the person は続く I respect の目的語になっている。
だから関係代名詞を省略している。
では、もし省略しないとしたらどれ?
A) person that I respect …
B) person who I respect …
C) person whom I respect …
正解は
「全部」
Real Life English(Writing)
p.69
記事への意見 ─ 投稿文 ─
text(ing):<動詞> 「メールを書いて送る」
ban(ned):<動詞>として、「禁止する」。
日本語でも最近よく聞く。「バンされる」のバン。
electronic:<形容詞> 「電子の」。
アクセント位置注意 /エレクトロニク/
device(s):<名詞> 「機器」「デバイス」
cross:<動詞>「横断する、渡る」
decision(s):<名詞> 「(考えて下した)決定」
bother:<名詞>として、「面倒」。
<動詞> として「面倒なことをする」、「わざわざする」「人を不愉快にさせる」「モヤモヤさせる」などの意味があり、日常ではよく使われる。
common:<形容詞>「一般的な」「日常的な、普通の」
Grammar 3 – 後置修飾
>>> 後置修飾 〜情報を加える〜
p.70, p.71
後置修飾について。ここはほんとうに重要。
これが英語の肝であり、もっとも難しい部分。日本人が英語が苦手な原因。なぜなら日本語には存在しない表現方法だから。
”名詞の後ろから(あとから)説明を加える”、という英語思考。ここのページはとても丁寧に良く書かれているのでしっかり読んでおこう。
「なんだ、あれもそれも後置修飾だったんだ。」
と思うかもしれない。
以上、第36回『ニューホライズン3』ユニット5
関連図書:

ワーク&テスト ニューホライズン 3年
引用元:

東京書籍 令和7年4月新刊 中学教科書 NEW HORIZON English Course 3 [教番:英語002-92]
東京書籍 発行