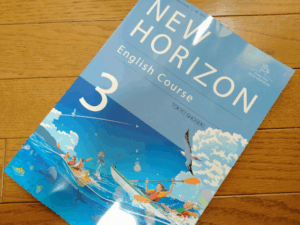第36回 中3ユニット5:P61- P71『 ニューホライズン3』単語, 文法ガイド
このページは旧版(令和3年版)です。
・『New Horizon』シリーズ目次
・旧2025令和7年度版(1ページ目)
Unit.5 – A Legacy for Peace
p.71
legacy:<名詞> もともとは「相続遺産」という意味。
そこから派生して、「後世代に受け継がれるべき”物”や”出来事”、あるいは人物の功績」「レガシー」
Gandhi:<人名> 「ガンディー」。
”Mahatma Gandhi”として欧米圏でも名が知られている人物。覚えておいて損はない。
p.72
Preview
p.73
– Scene.1 /
ジョシュがガンディーについて紹介
[名詞を後ろから修飾する文] [KS-15]
rupee notes:<名詞> インドの「ルピー紙幣」。
“note”<名詞><英>は”banknote”の省略形で、「中央銀行が発行した紙幣」で、要は「お札」のこと。
特にイギリスで使われる言い方。アメリカでは”bill”を使うのが一般的。
person:<名詞> 「(特定の)個人」。複数形は文脈によるが、
“persons”「その特定の個人の集まり」。
“people”は、特定された個人ではない「一般の人々」というイメージ。
─ ”目的語”となる関係代名詞 ─
“a person [that/who/whom] Indian people respect”
で、personを後ろから形容(後置修飾)している。
この場合は目的格の<関係代名詞>。
この時、以下の4パターンで使われることがある。どれももちろん意味は同じ。
よく使われる(見かける)順に─
[1].本文の様に関係代名詞を省略する。
[2].thatを使う。
[3].whoを使う。
[4].whomを使う。
少しカタコト日本語でもいいから語順の通り理解できるように練習しよう。
「一人の人物、多くのインドの人が尊敬した」
respect:<動詞> 「尊敬する」
greatly:<副詞>で動詞を修飾する。「とても」「たいへん」
born:<形容詞><過去分詞> 「生まれる」。Be動詞とともに受け身形で使う。
もとは”bear”<動詞>「(ものを)運ぶ」の<過去分詞>の形。
international:<形容詞> 「国際的な」
non-violence:<名詞> 政治や社会的問題に対して「非暴力(主義)」
p.74
– Scene.2 /
ジョシュと朝美がガンディーについて話している
[関係代名詞 who]
independence:<名詞> 「独立した状態」。/インディ-ペンデンス/
violence:<名詞> 「暴力」
fight:<動詞> 「戦う」。
不規則動詞で<過去形><過去分詞>ともに”fought”と変化する。よく見るので覚えよう。
ちなみに発音は/フォート/。
「〜のために戦う」という使い方が多く、前置詞”for”とともに使う。
human rights:<名詞> 「人間の諸権利」=>「人権」。人には様々な権利があるので、複数形で使う。
go on:<句動詞> ここでは「取り掛かる」「始める」の意味と、「続ける」の意味の両方が合わさったイメージ。
“on”の「上に乗せる」イメージと、「すでに乗っかっている」イメージとで”go on”の意味にバリエーションが与えられる。
fast(s):<名詞> として、ここでは「断食(だんじき)」の意味。「速い」の”fast”とスペルは同じ。
protest:<動詞> 「抗議する」。/プロテスト/。アクセントの位置に注意。
“to protest”は<to不定詞>の副詞的用法。「抗議のために」
tough:<形容詞> (どうにか耐えられるだろうけど)「厳しい」
“That(It) sounds …” 「〜に響く/聞こえる)」=>「〜(な感じ)ですね」
五感系の表現はいろいろ。この場面では”It looks tough.”とは言わないだろう。見てはいないし。
では、”seems”はどうだろう?「〜みたいですね」これは使える気がする。
見(see)てはいないが、聞いた発言から想像して自分の頭にイメージして「〜のようですね」。
p.75
Mini Activity
リスニング、スピーキング、ライティングの練習。
Unit.5 – Read and Think
p.76, p.77
– Read and ThinK (1) /
朝美はさらにガンディーについて知るために、伝記を読んでいます。
(ここは”NewWords”に和訳が付いていますので、<句>のみ解説します。)
at that time:<副詞句> 「その当時は」「その時は」。長い時間幅があるイメージ。昔話などもこちらの表現。
“at the time”は「その時」。短い時間で最近の出来事を語る時のイメージ。この前の出来事など。
“at a time”だと「一度に」という別の意味に。
─ ”主語”となる関係代名詞 ─
“made a law that (=a law) was even more unfair …”
that以下は、”a law”を後ろから限定的に説明している。
語順通りに訳すと「ある法律を作った、それはさらにアンフェアだった」
“made”の目的語の”a law”だったが、
<関係代名詞>”that (=a law)”で今度はそれ以下の文の主語の役割となった。
この<関係代名詞>が主語となる場合は、省略しない(目的語になる場合は省略できる)。
stand up:<句動詞> 文字通り「立ち上がる」。その後に前置詞が続くと意味が以下のように派生する。
“stand up against …“「〜対して立ち向かう」
“stand up to …“「〜に対して立ち向かう」
日本語では同じ意味になるが前置詞のもつイメージに引っ張られる。
“against”は法律(本文の”the law”)や物事などに対して。”to”は人に対して。
“stand up to the bully” 「そのいじめっ子に立ち向かう」
even if:<副詞句> 「たとえ〜だとしても」。evenはifを強調している。この辺りは日本語の感覚に近い。
“if”「もし〜なら」とは違う感覚。
in those days:<副詞句> 「そのころは」
上に出てくる”at that time”と何が違うのか?これも日本語の感覚に近い。
日本語で「あの当時は」と「その頃は」とは何が違うのか?
ほぼ同じ意味だ。だけど言い回しを変えたいのだ。
特に英語ネイティブは、同じ単語や用語(名詞は除く)を連続して使いたくない人たちである。
“a law that (=a law) British made for salt”
「ある法律、イギリスが塩(の取引)のために作った」
<関係代名詞>の”that”は”there is”の目的語(補語)になっているので省略もできる。
thousands of:<句><口語> 「何千もの〜」「多くの〜」。1,000を複数形にして表現する。
数としては、頑張れば数えられるくらい。
“tens of thousands of …” や “millions of …” になると数えられないほどの大量な数の表現になる。
p.78, p.79
– Read and Think (2) /
朝美はさらにガンディーについて知るために、伝記を読んでいます。
[関係代名詞 that/which(主格)]
[KS-17]
[関係代名詞 that/which(目的格)]
[KS-18]
リードアンドシンク(2)では本文の要旨把握と、キーセンテンス。
[KS17]は、[関係代名詞 that/which(主格)]に関する文。
[KS18]は、[関係代名詞 that/which(目的格)]の文。
共に上で説明した。
ここのリードアンドシンク2は、前のページ文章の読解問題と関係代名詞のまとめ。
discrimination:<名詞>「差別」。
人種、肌の色、出身地、宗教、年齢、性別、身体、すべての差別に使う。
発音は、/ディスクリミネーション/
independence:<名詞>「独立」。
特に権力に制限されていない自由な状態。
発音は、/インデペンデンス/
dependence は反対の意味になって、「依存」とか「従属」となる。
non-violence:<名詞>「非暴力」
特に政治的・社会的な変化を力を使わずに起こすこと。
unfair:<形容詞>「不公平」。
アメリカ人はたぶんこの言葉に一番反応する。
これらの単語は、日本にいるとあまり強く感じることは少ないかないかもしれない。
だけど世界を見渡すときには必要となる。
p.80
Unit Activity
あこがれの人物はだれ?
Let’s Write (3) – グラフや表の活用 ─レポート─
p.81
growth:<名詞>「成長」「増大」
populous:<形容詞>「人口の多い」
powerful:<形容詞>「パワフルな」「強大な」
billion(s):<限定詞><数>「10億」。
数で表せば、1,000,000,000。
grammar (3) – 後置修飾
p.82, p.83
後置修飾について。ここはほんとうに重要。
これが英語の肝であり、もっとも難しい部分。
日本人が英語が苦手な原因。
日本語には存在しない表現方法。
”名詞の後ろから(あとから)説明を加える”、という英語思考。
p.88
人物の経歴を聞いて概要を理解する。
以上『ニューホライズン3』ユニット5
このページは旧版(令和3年版)です。