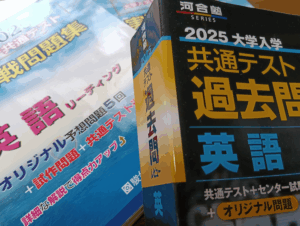2023年令和5年度『共通テスト英語』:65点からあと10点をどうするか考える
過去5年分の『共通テスト英語』:平均点や語彙数・正答率を比較分析をする
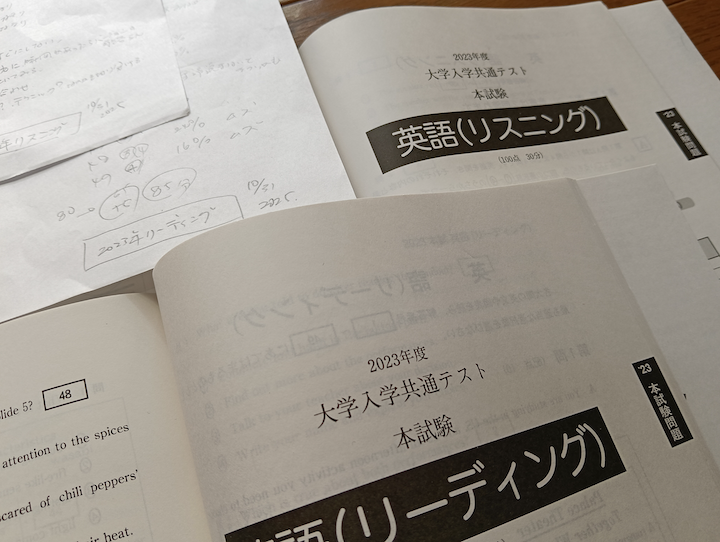
(DEEY─)『共通テスト英語』過去問シリーズ、今回は2023年1月実施の令和5年度をやっていきます。
これを書いているのは2025年11月で、今年から問題構成と内容が一部変更になったので、2023年はひと世代前のフォーマットということになります。
ですが基本的に問われることに大きな違いはないので十分演習の効果はあります。
1)過去問の解き方について
過去問のやり方ですが、(1)時間を測って解いて、(2)すぐに答え合わせはしない。(3)もう一度「延長時間(測っておく)」として解く。
という感じでやります。「はー終わった。さて答え合わせ」とはしないで延長線をやりましょう。
それは「時間さえあれば解ける」ことを確認したいから。もし時間があっても解けないのであればそれは「単語」と「文法」です。
そのために付録のマークシートを使うというよりはノートを使って、各解答の右にスペースをエクストラタイム用として開けておく。
解答を見る前の解き直しで、もし解答を修正するなら、最初の解答は消さないで修正解答は右に追記しておく。
これはリスニングも同じ。特にリスニングは2回聞いてわからないなら3回聞いてもいい。なんだったら4回でも。
たいていは3回聞いて無理なら、それ以上聞いても変わらないでしょう。
でもとにかく解答英文スクリプトを見る前に「何が聞き取れなかったか」をはっきりさておきたいのです。
たいていは「英語音」->「イメージ」変換の時間がかかってしまい置いていかれるという展開でしょう。
ということで問題を見ていきましょう。
2)2023年度リーディング
試験内容構成の変化に加えてもう一つ2025年度で変わったことは、試験の順番。これまではリスニングが先でした。高校入試もリスニングが先。TOEICもリスニングが先。
それがどう言うわけかリーディングが先になりました。
ということで先にリーディングパートからいきましょう。
リーディングは80分。設問数は「49」。語彙数は問題文や選択肢文含めて「6,150」語。平均点は「53.81」点。標準偏差は「20.99」。
つまり、もしこの2023年度リーディングテストで80点を取れたなら(これを確率変数Xとする)、
標準化した確率変数Zは、
Z = (取得点-平均点) / (標準偏差) = (80-53.81)/20.99 = 1.248 -> p(1.248)
つまり、P(X>=80) = P(Z=>1.248) = 0.5 – 0.394 = 0.106
あなたは上位10.6パーセントの実力だということになります。
偏差値は、((取得点-平均点) / (標準偏差))×10+50 = 62.48
さて問題構成は以下の表。併せて「最後49問まで解き切る」パターンの想定タイムを載せました。
| 大問 | 大問ブロック | 設問 | 配点 | 理想セットタイム |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | A | 1, 2 | 4点 | 3分 |
| B | 3, 4, 5 | 6点 | 4分(7分) | |
| 第2問 | A | 6, 7, 8, 9, 10 | 10点 | 7分(14分) |
| B | 11, 12, 13, 14, 15 | 10点 | 8分(22分) | |
| 第3問 | A | 16, 17 | 6点 | 5分(27分) |
| B | [18-19-20-21], 22, 23 | 9点 | 6分(33分) | |
| 第4問 | – | 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 16点 | 11分(44分) |
| 第5問 | – | [30-31-32-33], 34, [35-36], 37, 38 | 15点 | 12分(56分) |
| 第6問 | A | [39-40], 41, 42, 43 | 12点 | 11分(67分) |
| B | 44, 45, [46-47], 48, 49 | 12点 | 13分(80分) |
80点目標として第3問が終わった時に35分を超えていると、最後まで問題を解き切るのは難しいでしょう。読むことはできても問題まで手が届かない。
共通テストのリーディングがこのように速読と内容一致に限られているので、結局は日本語の国語力も問われていることになります。
国語ができる人かどうか、普段から本を読む習慣があるかで差がつく。
そう言う意味で例えば65点の取り方もふた通りに分かれている感じがあります。
一人目はざっくりと最後まで到達できる人、でも全体はぼやけている感じ。
もう一人は速読できないけど比較的ピント合わせて読み込んで、で大問6の途中くらいで時間切れのひと。
前者は100%読み切って正解率6割5分の65点。後者は80%到達して正解率8割の65点。
ここから数ヶ月で10点上乗せするために、前者はどうやってピントを合わせてるか、後者はどうやって速度を上げるか、と戦略は異なります。
印象としては前者のタイプは「単語や文法が多少あやしくても想像しながら、わからないなりに読める人」
後者は「わからないまま進むのはモヤモヤするので、確実に読んでいきたいタイプ」
前者は「単語力」や「文法力」の向上であっという間に10点は上がるイメージです。
後者のスピードが上がらないタイプは、単語力や文法力は高い人も多い。それゆえにきっちり行かないと気持ち悪いと感じる。
このタイプの人は多少わからなくてモヤモヤしながらも「早く読む勇気」をもつ練習、「全体をぼんやりでも捉える」練習をすることだと思います。
3)2023年度リスニング
続いてリスニング。
リスニングは30分。設問数は「37」。平均点は「62.35」点。標準偏差は「18.82」。
リスニングは例年リーディングよりは平均点が高い。
そして標準偏差は2ほど小さい。これは平均点からの得点ばらつきがリーディングよりは小さいことを意味しています。
リーディング同様に2023年リスニングが80点取れたとすると、これを確率変数Xとして
標準化した確率変数Zは、
Z = (取得点-平均点) / (標準偏差) = (80-62.35)/18.82 = 0.938 -> p(0.938)
つまり、P(X>=80) = P(Z=>0.938) = 0.5 – 0.326 = 0.174
ということでリスニングは同じ80点でも、上位17.4パーセントの実力ということになります。
偏差値は、((取得点-平均点) / (標準偏差))×10+50 = 59.38
リスニングの問題と構成表も載せておきます。
| 大問 | 大問ブロック | 設問 | 配点 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | A | 1, 2, 3, 4 | 16点 | 音声2回 |
| B | 5, 6, 7 | 9点 | ||
| 第2問 | – | 8, 9, 10, 11 | 16点 | |
| 第3問 | – | 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 18点 | ここから音声1回 |
| 第4問 | A | [18-19-20-21], 22, 23, 24, 25 | 8点 | |
| B | 26 | 4点 | ||
| 第5問 | – | 27, [28-29], [30-31], 32, 33 | 15点 | |
| 第6問 | A | 34, 35 | 6点 | |
| B | 36, 37 | 8点 |
リスニングについては過去問や模試、演習問題をひたすらこなして慣れることをおすすめします。
ただ何時間もやる必要はないです。その代わり理想は週5日、1日大問ひとつくらい、30分くらい。
「言葉」とはとにかく「毎日使うことが普通」なのでそれに近づけたい。
とくに聴きながら図表を見ながらメモを取れる練習をすること。
それから今回2023年第4問のようにイギリス英語が出てくることもあります。第5問はインド人?
発音だけではなく抑揚も違うので慣れが必要です。
それからリスニングの模試や本番で大事なのは「先に行く勇気」「捨てる勇気」。
「つづいて第4問です。第4問はAとBの二つの部分に…」とアナウンスが聞こえてきたら、その時点では第4問の先読みをしていなければいけません。
少なくとも目の前の問題は「あきらめる」。
理想は、
解答をマークし終える
-> ページめくりながら2から3秒間一瞬休憩(息継ぎ)する
-> 次の問題を先読みし始める
-> 次の問題のアナウンスが聞こえてくる
というような流れとリズム。一瞬休憩するのもリズムに一役。
この辺りに慣れるために、例えば大問を2つ続けて演習して感覚をつけておくという手も。
(2025年11月)

共通テスト過去問研究 英語 リーディング/リスニング (2026年版共通テスト赤本シリーズ)

2026-大学入学共通テスト 実戦問題集 英語リーディング (駿台大学入試完全対策シリーズ)