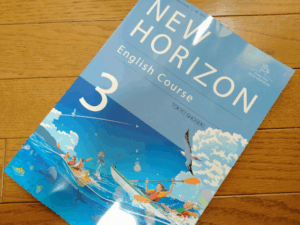第38回 中3ユニット6:P77- P87『ニューホライズン3』単語, 文法ガイド
このページは旧版(令和3年版)です。
・『New Horizon』シリーズ目次
・旧2025令和7年度版(1ページ目)
『ニューホライズン 3』
─ 目 次 ─
p.89
- Grammar – 仮定法
p.101
Unit.6 – Beyond Borders
p.89
beyond:<前置詞>として、「〜を超えて」
border(s):<名詞>として、「国境」
relation(s):<名詞> (2つかそれ以上の人々や物事の)「関係」
p.90
Preview
p.78
– Scene 1 /
国際協力のキャンペーン広告
[仮定法: I wish … ]
backpack(s):<名詞>として、「バックパック」、「リュック」。ここでは「ランドセル」の英訳。
this way:<名詞句> 「この様」「こんな風」。
“feel(felt) this/that way” は会話ではよく出てくる。「こんな風に感じる」「そんなように感じた」。
“this”と”that”では心理的な距離感が違う。昔のことや何か他人が言ったことを思い出しながら言うなら”that”を使いたい。
campaign:<名詞> ある目的を達成するための組織的な手段や手順や運営。「キャンペーン」
このような組織的な運営行動は、選挙”活動”や企業”経営”など動詞は “run” を使うことが多い。
run a company 「会社を運営する」、とか
run for president 「大統領に立候補する」、とか。
unused:<形容詞> 「使われていない」。
un + use + ed で「否定」+「使う」+「過去分詞形」。
<過去分詞>を「〜された」という意味で<形容詞>として用いて次に来る<名詞>を修飾している。
supply, supplies:<名詞>として、「支給されたもの」
donate:<動詞> 「寄付をする」
p.92
– Scene.2 /
海斗はメグに海を渡るランドセルの話をしています。
[仮定法(If + S + were …)]
Afganistan:<名詞><国> 「アフガニスタン」。アジアの中央にある国。発音するときは”ガ”にアクセント。
インドの西側にあるパキスタンの西側。イランの東側。
so far:<慣用句><副詞句> 「今のところ」。
“far”は「遠い」の意味から「(それなりの)範囲」という意味でも使う。
教科書では文頭にあるが、文末に置いてもいい。
─ 仮定法過去 ─
“If I were a Japanese student, I would send my old backpack.”
「私がもし日本の生徒だったなら、自分が使い終わったランドセルを贈ってあげたでしょう。」
[仮定法過去]と呼ばれよく用いる表現。日本語でも「自分だったら、それやってたのに。」みたいな言い方は日常的な表現だと思う。
そして日本語でも”実現していないこと”に関してはやっぱり[過去形]で表現してる。だから[仮定法過去]という名前。
で、同じ様に英語も過去形を使う。
“If I were you, I would do that.”
「てたのに。」の感じを出すのに”would”を使う。
“If I were you, I did that.”
だと変な文。聴く方は”would”を補って聞いてくれるから多分意味は通じるけど、カタコト英語。
前ページのScene.1の”wish”を使ったやつ
“I wish (that) I could do that.”
「それ、やることができたらなぁ」
も”that”以下は過去形。日本語でも過去形。
“I wish I would do that.”
はちょっと変な文。”would”は”will”の意味を含むから「意思」を表明している。
「それをやる意思のある強い人間だったらよかったのに…」的な意味になりそう。
まあ、わからなくもないか。
definitely:<副詞> 「必ず」「間違いなく」。
発音とアクセント位置注意。/ デフィニトリ/
p.93
Mini Activity
仮定法の使い方を学ぶコーナー
Unit.6 – Read and Think
p.94
– Read and Think (1-1) /
海斗はキャンペーンについて調べたことをスピーチしています。
[仮定法(If + S + 動詞過去形)]
[主語を後置修飾する関係代名詞]
─ 後置修飾について ─
この長文読解セクションでは[仮定法]に加えて、[後置修飾]の文が多用されている。
英語の本質はこの[後置修飾]と言ってもいいくらいなので、ここではこの説明をしたいと思う。
[後置修飾]は日本語システムと英語システムの大きく異なる点でもあり、リーディング(黙読)の時、これを日本語の様に後ろから訳してはいけない。
それをやっていると英語は上達しない。
試験問題で「日本語に訳しなさい。」と言われたら仕方なく日本語らしく書く。
「意味がわからないことを言ってる」と思われている気がするけど、具体的に以下で説明する。
[後置]だから”後ろから訳す”ではない。英語だって日本語だって頭から語順の通りに理解するものだ。
あと、ここの”New Words”は、日本語訳がすでに書いてあるので全部は触れない。必要だと思ったらここでも触れよう。
“life without school“:<前置詞>による[後置修飾]。
例えば、これを読むときは「人生(生活)」->「付属していない」->「学校」と言う順番で頭の中で絵を描く。
これを全部最後まで読んでから、後ろから「学校のない人生(生活)」と訳して頭に絵を描いて納得するのでは─
遅い。
リスニングでは置いていかれる。
同様に以下も<前置詞>による[後置修飾]。
もう、そればっかり。英語は。
“information through books …”
“parts of ..”
同じように語順通り頭からイメージする練習をしよう。
“illiterate“:<形容詞>「読み書きのできない」。発音アクセント注意。/イリタレイト/
“children living like this“:<動名詞>による[後置修飾]。
<動名詞>による[後置修飾]も頻繁に見られる。
この<動名詞>の意味上の主語が誰なのか?は時々難しいことがある。
けど、そのわかりづらいのは話す人の責任だったりする。
この文では”living”しているのは(主語は)直前の”children”。
「こどもたち」->「住んでいる」->「のように」->「この」
この文は関係代名詞が省略されている、と思ってもいい。
“Children who are living like this”
でも同じ意味。
“encourage A to B“:<句> 「A(人/物)にBするように促す(励ます)」
“make”は強制感や無機質感あるけど、”encorage”は自主的にやる感じかつウエットな感じ。
“most of …“:<代名詞句> として。「ほとんどの」
“most backpacks”とすると「世の中のカバンのほとんど」の意味になってしまう。
“be ready for …“:<慣用句>「用意ができている」。
“ready”は「レディー」で日本語になってる。後には前置詞の”for”を使う。
“in the open air“:<慣用句> 直訳すれば「開かれた空間の中で」
“air”は「(地球上の)空気」だが、そこから「閉じ込められていない地表」的な意味でも使う。
“the open air”と”the”が付いているので、「そこの屋外」
「学校の校舎がない地域では、子供達は屋外でランドセルを机として使えるのです。」
“from one A to another (A)“:<慣用句> 「1つのAからその他の(A)まで」
これもよく使われる表現。ひとつのものから次のものへ、数珠つなぎに現象が起きている感じ。
本文では、”A”は”contry”で、また”another”の後ろの”country”は繰り返しになるので省略する。
“all around the globe“:<句> 「地球上のどこでも」
“all”は<副詞>的に「全て」の意味で”around the globe”を修飾(強調している)イメージ。
“only lines on a map“:<句>「ただの地図上の線」
ここの文脈では “only” ではなく “just” のほうがいいと思われる。
“only” の<形容詞>は量的数的に「たったの」「唯一の」というニュアンスであって、「単なる」ではないと思う。
「線画アート」であれば “artwork with only lines” でいいだろう。「線だけで描かれた絵」
先生に聞いてみて欲しい。
p.95
– Read and Think (1-2) /
<<右側:2ページ目>>
“depend on …“:<句動詞>というほどでもないが、「〜を(信頼して)頼る」「〜によってコントロールされている」
便利な単語で、日本人が大好きな言葉。こればっかり使ってしまいがち。
prefix<接頭辞> “in”が頭についた<形容詞>は、反対の意味になって
”independent” <形容詞>「独立した」
“independ”という<動詞>はなぜか、ない。
“Many things that …“:「いろいろな物」と言ってから<関係代名詞>”that”を使って[後置修飾]。
“that=many things”は[目的格]で直後の”we see”の目的語。
[目的格]の”that”だけど省略しないの?
この場合は自分ならやっぱり省略しない気がする。省略した表現も違和感はないが。
“such as …“:「例えば」
“for example“:「例えば」
“like …“:「例えば」
「例えば」三連発。同じ言い回しをしたくないので表現を変える。
“If we didn’t … , fried chicken would be …” :[仮定法過去]
“many products that are sold …“:<関係代名詞>による[後置修飾]。
「多くの製品」->「売られている」->「日本の会社によって」
“that = many products”は主語。
ここからは余談。
“many products sold by …”のように、”that are”を省略する文章にもできる。
形としては<過去分詞>による[後置修飾]という呼び方になるが、意味は少し変わってしまう。
これだと「日本の企業に売られた多くの製品」と過去の話になってしまう。今はどうか分からない。
なので<現在分詞>を使った受動態の[後置修飾]にすると同じ意味にできる。
“many products being sold by …”
とすると関係代名詞を使わなくても表現できる。
“no exception“:<句>「例外なく」。よく使われる表現なので覚えておく。
ただし強い意味があるので人に対しては使わないようにする。政治家や社長なら別。
事実に対して使う。
“interdependent“:<形容詞>「相互に依存した」。/インタ-ディペンデント/
<接頭辞>の”inter”で「お互い」とか「間の」という意味が付加される。
インターネット、インターナショナル、インターセプト、インタラクト、インターセクション
などなど、日本語でもいっぱい。
“It’s A for B to do C“:<慣用節>「B(人)にとって、CをすることはAである。」
これもよく出ててくる表現。
“To continue helping each other is necessary.”でもいい。けど主語が長い。
だから「必要なこと」”It is necessary”と先に言ってしまう表現方法。
「私たちにとって必要」だから”for us”と続けて、そのあとに<to不定詞>をさらに続ける。
p.96, p.97, p.98
– Read and Think (2)
[ 仮定法過去(一般動詞)]
[ 主語を説明する関係代名詞 ]
リードアンドシンク(2)は、前ページ(1)の文章に関しての要約やまとめの練習。
そのあとでキーセンテンスが出てくる。
[KS-21]は、[仮定法]で一般動詞を使うときはどうなる?
「もし…だったら、〜だろうに。」の
「だろうに」
はどう表現する?
このとき例文のように、<助動詞> “would” や “could” をつかう。
次の[KS22]は、関係代名詞の目的格の使い方のバリエーション。
名詞は主語になり得る。=>
関係代名詞は名詞を後置修飾する。=>
結果、場合によってはすごい長い主語が出来上がることがある。
という話。
p.98
Unit Activity
100人の村の世界
Let’s Talk (3) 食品の選択
p.99
─ 賛成する・反対する ─
ここでは、ある考え(thought)に対して、賛成(agee)や反対(I not sure)の表現。
そう思う理由(Reason)を述べる練習をする。
都立入試や英検の英作文ではこのページで扱う、
”自分の考えを述べる”
+(プラス)
”なぜそう思うか理由を述べる”
という2段階の作文方法を学んで、取り入れると良いと思う。
言い回しや表現など。
domestic:<形容詞>「国内の」。もともとは「家庭内の」という意味。
cheap(er):<形容詞>「安い」
本文では “cheaper” 以下の “than imported ones” は省略されている。
in season:<副詞句>「旬で」。季節(シーズン)の中にある、ということで。
seem:<動詞> 「〜のような印象を受ける」
“look” が「〜に見える」、”sound” が「〜に聞こえる/響く」と同じカテゴリー。
transport(ing):<動詞>「乗り物で人や物を運ぶ」
food mile(s):<句><イギリス英語>「フードマイル」
食物で、生産地から消費地までに必要な輸送距離をいうらしい。移動のための必要な燃料を環境への影響と捉える。
point:<名詞> 「ポイント」。ここでは「主張」とか「アイデア」の意味。
agree <=> disagree:<動詞> 「同意する」<=>「同意しない」
“disagree” は日本語訳同様に「同意しない」と言い切るので、かなり強い言い方になる。
だからこれを実際に使うと、だいたい言われた方は怒る。
テレビの討論番組や国会中継さながらの敵対的な雰囲気になる。ひろゆきやホリエモンの空気感になる。
だから日常では教科書にもあるように、
“I’m not sure, but …“:「自分にはよくわからないけど…」
とか
“You may be right, but …“:「多分あなたの言ってることは正しいのかもね、だけど…」
のような日本語にもある婉曲的な言い回しを使う。
”英語は言いたいことをはっきり言う”と言うのはかなり間違った認識だと思う。
人種が多様な国では、自分の発言は慎重にしておかないと誤解を生むし物理的に傷つく可能性が高い。
agree with A:<句> 「Aと同じ意見である」
besides:<副詞> 「(それに)加えて」「さらに」
■ Grammer (4) 仮定法
p.100
仮定法
■ Let’s Listen (6) 中学校生活の思い出
p.101
スピーチを聞いて概要を理解する。
以上『ニューホライズン3』ユニット6
このページは旧版(令和3年版)です。