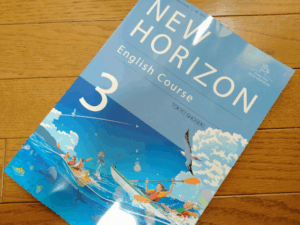第33回 中3ユニット3:P31- P41『二ユーホライズン3』単語, 文法ガイド
『New Horizon』シリーズ目次
旧2021令和3年度版(2ページ目)

(DEEY─)英語の授業の予習をしようと思ったけど、単語を調べるのが大変─
中学教科書『ニューホライズン(東京書籍)』の 単語・用語解説シリーズ、第33回は『New Horizon 3 』
・ユニット3
・31ページから41ページまで
をやります。
見かた、使い方
新単語は以下のような”凡例(ルール)”にしたがって記述しています。
─ 凡例 ─
word(s) <品詞> 「和訳」 。〜説明〜
phrase <句>「和訳」。〜説明〜
英語は同じ綴りで<動詞>で使ったり<形容詞>で使われたりします。そのためここでは”どの<品詞>”で使われているかも併記します。
“<名詞>として(使われている)。”
と書かれていた場合は、その単語はいくつかの品詞の種類があるけれど、本文では<名詞>として使われていることを示します。
“<名詞>”
とだけ書かれている場合は、その単語はほとんどの場合<名詞>以外の用法はないことを示します。
ラッキー。
『ニューホライズン 3』
─ 2025年版 目次 ─
p.31
Unit.3 – How can we save animals?
p.34
Unit.3 – Read and Think 1
p.38
Unit.3 – Unit Activity
Grammar 2 – 不定詞
p.41
Unit.3 – How can we save animals?
p.31
ユニット3は不定詞。不定の詞。定めない詞。ある時は名詞、ある時は副詞、ある時は形容詞。そして常に原型。定めを受けない詞。
さて不定詞は一年振りでその時は副詞用法・形容詞用法だった。さらにその一年前は名詞用法だった。want to, need to のやつ。
3年の今回の内容は名詞用法のバリエーションとでも言うべきか。
・It is … to不定詞のバリエーション
・SVOOの2つ目のOがto不定詞のパターン
・SVOOの2つ目のOが原型不定詞のパターン
全て頻出の構造なのでしっかりとやっていく。
p.32
– Part 1 /
英語のポスター
[ It is … for 人 to 不定詞 … ]
[KS-8] It is … for … to do …
パート1では to不定詞が主語になる名詞用法の変形
It is A for B to不定詞 ….
の型。例えばこんなような文を考える。
「毎日そのドラマを見ることが必須」
・To watch the drama every day is necessary.
この文これはこれでOK。
ただこう言う時「主語が重たい(長い)」として It を仮の主語にして、To以下を後ろに持ってくるのだった(中2)。
・It is necessary to watch the drama every day.(仮の主語it と to不定詞)
今回はこれに「意味上の主語(誰にとって)」を足したいときどうするか?という話。
答えは、for[人]をそこに挟み込む。
「毎日そのドラマを見ることが自分に取っては必須」
・It is necessary for me to watch the drama every day.
danger:<名詞> 「危険」「危機」
be in danger of …:<句> 「〜の危機にある」。
SVCでCが主語の性質や状態を説明する時、C = 前置詞+名詞のパターンがある。
extinction:<名詞> 「絶滅」
challenge(s):<名詞>として、「(困難な仕事や状況に対する)挑戦」「(目上の人や権力に対する)挑戦」。
球技系スポーツを見る人は知っているだろう。サッカー、野球、テニス、アメフト…
審判の判定に対して意義を申し立てて、ビデオ判定に持ち込むことを「チャレンジ」と呼んでいる。
climate:<名詞> 「気候」
human:<形容詞>「人間の、人の」
endangered:<形容詞> 「絶滅危機にある」。danger が<名詞>。
en + dander で<動詞> 「危険な目に遭わせる」。
en + danger +ed <過去分詞> = <形容詞>
survive:<動詞> 「生き残る」
condition(s):<名詞> 「状況」「コンディション」
trouble:<名詞>「面倒、厄介なこと」「トラブル」
p.33
– Part 2 /
絶滅の恐れのある動物
[ … want 人 to 不定詞 ]
[KS-9] … want … to do …
パート2は第四文型SVOOの後ろのOにto不定詞の名詞形が入るパターン。
「SVOOってなんだっけ?」という人は要復習。目的語を二つ取る動詞とその文型のことだった。
この二つ目の目的語に名詞としてのto不定詞を置いてもいい。
「君にその映画を見てほしいわ」
・I want you to watch the movie.
「彼にその映画をテェックするように伝えて」
・Tell him to check out the movie.
このパターンを取れるかどうかは動詞による。ask, advise, allow とかもそう。
the Red List:<固有名詞> 「レッドリスト」。
絶滅危機にある生物の種のリスト。
hear of …:<句> 「(情報や話などを)聞き及ぶ」「耳にする」。
hear は「聞く」「聞こえる」。このof がつくパターンには、know of, think of, make of などなどがある。
cheetah(s):<名詞> 「チーター」。
「ずる」や「裏切る」の「チート」は “cheat”
sea otter(s):<名詞>「ラッコ」。
otter は「カワウソ」
article:<名詞>「記事」
Unit.3 – Read and Think 1
p.34, 35
– Read and Think 1 /
ラッコの数が減っている
[ let / help 人 動詞原型 ]
[KS-10] Let … do …
… help … do …
次にSVOO型の2番目のOにtoの付かない不定詞─ <原型不定詞>を使うパターン。
この形を取る動詞はここでは “help” と “let”。
「その映画を見させた(許可した)。」
・I let him watch the movie.
特徴は2つ目の目的語は動詞の原型を置くこと。make や have もそう。
ちなみに help は、
「映画をDVDで見るのを手伝った。」
・I helped him watch the movie DVD.
・I helped him to watch the movie DVD.
どちらでもよい。今は”to” を付けない方が一般的。
population:<名詞> 「そこに生息しているものの数」。
人間なら「人口」。
rapidly:<副詞> 「急速に」。
日本語でも”ラピッド”は時々見かける。電車の快速は “rapid “
as a result:<句>「結果として」
beginning:<名詞>「初め」
century:<名詞>「世紀」
shock(ed):<動詞>「「ショックを受けた」。
ショックを与える」の過去分詞。受動体で使われることが多い。
safely:<副詞> 「安全に」
overhunting:<動詞>「乱獲する」。
単語の頭につくoverで「やりすぎ的」なイメージを付加している。overdo「やりすぎる」overthrow「暴投する」
Thanks to …:<句>「〜のおかげで」
due to …:<句>「〜のせいで、原因で」
oil:<名詞>「石油、油」
spill(s):<名詞>「こぼすこと」「流出」
hunting:<名詞>「狩、狩猟」
killer whale(s):<名詞>「シャチ」
the surprising end:「驚くべき結果」
the end of the table:「そのテーブルの端っこ」
Unit.3 – Read and Think 2
p.36, 37
調べたことを記事としてまとめる。ここは新たな文法事項はなし。
one such animal:「ひとつのそのような動物」。such a animal だと「そのようなある一匹の動物」
native:<形容詞>「その土地の」「ネイティブの」
logging:<名詞> 「ビジネスとしての伐採」。
habitat:<名詞>「生息地」
traffic accident(s):<名詞>「交通事故」。
traffic も accident も名詞。
research:<名詞> 「研究」「調査」「リサーチ」
categorize(d):<動詞>「分類する」「カテゴライズする」。
category のカテゴリーの動詞形。
critically:<副詞>「危機的に」。
クリティカルヒットの critical
citizen(s):<名詞>「市民」。
法的に居住を認められている人
ecosystem:<名詞> 「生態系」「エコシステム」
human being(s):<固有名詞>「人間」。
ホモサピエンス(Humans = Homo sapiens)という種(species)の生き物
relate(d):<動詞> 「関係する」「関係させる」。
relate A to B:<句動詞> 「AをBに関係付ける」。
─ relate to か be related to か? ─
relate A to B のような動詞の使い方は一瞬悩ましい。
能動態で習うけれど、実際は受け身で使われることが多いパターン。
“C relate A to B” は、
“A is related to B by C”
と言い直せる。教科書で言えば、
The ecosystem relates us to each other.
「その生態系が私たちをお互いに関係づけている。」
受動態で言い換えれば、
「私たちは生態系によって関係付けられている。」
We are related to each other by the ecosystem.
もちろんどちらで表現しても良い。
ただ relate のような「させる」という意味のある動詞の場合、
能動態とすると多くが無生物が主語(この場合は”生態系”)になることが多い。
だから人間は「させられる」立場になる。つまり受け身の立場だ。
surprised, excited, など「〜させられる」系表現はいくつかある。
action:<名詞>「行動、アクション」
take rubbish home:「ゴミを家に持ち帰る」。home が<副詞>で「自宅に」という意味になる
bring in rubbish:「ゴミを持ち込む」。bring rubbish in と考える。in は副詞で前置詞ではない。
Unit.3 – Unit Activity
p.38
絶滅の恐れのある動物の現状を伝えよう
crested ibis:<固有名詞> 「日本トキ」。
“crest” は鳥や動物の頭の目立つ飾り的なものを言う。トサカとか。トキの襟足の冠毛も印象的。
one by one:<副詞句> 「ひとつ、またひとつ」。
「次々に」と言うことだが、ひとつづつ(一匹づつ)という表現。”one after another” でも同じイメージ。
-born:<形容詞> 「〜生まれの」。
本文では “Chinese” という<形容詞>の語尾に付けて使っている。<形容詞> – <形容詞>という構成。
Real Life English (Writing)
p.39
グラフや表の活用
breed:<動詞> 「繁殖させる」。breeding は <名詞> で「繁殖」。
ちなみに発音が似てる “bleed” は「出血する」。『”l” と “r” を間違えると全然違う意味になるシリーズ』のひとつ。
release(d):<動詞>「解放する」。
「リリース(発売する)」の意味もある。
reach(ed):<動詞>「到達する」「(手が)届く」
nowadays:<副詞>「今や、今日では」
continue(d):<動詞>「続ける、継続させる」
all over:<句> 「至る所」(= everywhere)
Learning Science in English(理科)
p.40
GRAMMAR (2):不定詞
p.41
>>> 不定詞 〜「誰がするか」をとらえる〜
以上、第33回『ニューホライズン3』ユニット3
関連図書:

ワーク&テスト ニューホライズン 3年

【無料音声アプリ対応】高校入試 でる順ターゲット 中学英単語1800 四訂版 (高校入試でる順ターゲット)

中学校3年間の英単語が1ヵ月で1000語覚えられる本
引用元:

東京書籍 令和7年4月新刊 中学教科書 NEW HORIZON English Course 3 [教番:英語002-92]
東京書籍 発行