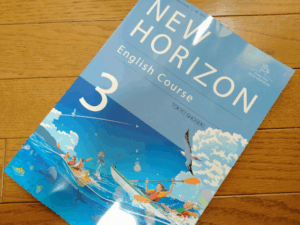第35回 中3ユニット4:P51- P60『ニューホライズン3』単語, 文法ガイド
『New Horizon』シリーズ目次
旧2021令和3年度版(2ページ目)

(DEEY─)現在完了形、不定詞が完了して一息。だけどここから文法的には登り坂で頂点を目指す。
それから教科書は4年に一度改訂していて、その度に文章量は増えている。単語も結構数多い。どんどん進めよう。
中学教科書『ニューホライズン(東京書籍)』の 単語・熟語・文法解説シリーズ。第35回は『New Horizon 3 』
・Unit.4
・51ページから60ページ
を解説します。
見かた、使い方
新単語は以下のような”凡例(ルール)”にしたがって記述しています。
─ 凡例 ─
word(s):<品詞> 「和訳」 。〜説明〜
phrase:<句>「和訳」。〜説明〜
英語は同じ綴りで<動詞>で使ったり<形容詞>で使われたりします。
そのためここでは”どの<品詞>”で使われているかも併記します。
“<名詞>として(使われている)。”
と書かれていた場合は、その単語はいくつかの品詞の種類があるけれど、本文では<名詞>として使われていることを示します。
“<名詞>”
とだけ書かれている場合は、その単語はほとんどの場合<名詞>以外の用法はないことを示します。
ラッキー。
『ニューホライズン 3』
─ 2025年度版 目次 ─
p.51
Unit.4 – How can we help each other in a disaster?
p.54
Unit.4 – Read and Think 1
p.60
Unit.4 – How can we help each other in a disaster?
p.51
ユニット4の文法は
・間接疑問文
・分詞
特に分詞は英語の核といっていい。
実は現在進行形も受動態も現在完了形も分詞を使っていた。
そう呼ばなかっただけで。
そしてさらに別の使い方がある。
p.52
– Part 1 /
外国人市民意識調査
[ 間接疑問文 ]
[SK-11] I know where …
疑問文が文の途中に入ると、その部分の語順は普通(肯定文)になる。
日本語でも例えば、「シェルターはどこにあるか知っている。」という文の中のには疑問文はない。
この「どこにシェルターがあるか」の部分を[間接的な疑問文]と言っている。
「その映画館が新宿のどこにあるか知っている。」
・I know where the theater in Shinjyuku is.
prepare(d): (prepare の<過去分詞>):<形容詞>として「準備ができた」。/プリぺァード/
disaster:<名詞> 「(人命が損なわれるレベルの)大災害」。/ディゾースター/
shelter:<名詞>として「(災害や悪天候から一時的に避難できる)場所」「シェルター」
store:<動詞>として「保管する」「備蓄する」。
本文では<助動詞>”should”の後に出てくるので<名詞>の「お店」ではなく、<動詞>として使われていると判断する。
in case of:<副詞句> 「〜の場合には」。
日本語でも「そのケースでは…」と言うが、この”case”のこと。「場合」とか「状況」の意味。
extinguisher:<名詞> 「消化器」。
正確には本文のように手前に”fire”を付けるが、慣習的に省略されることがある。/ィクス-ティングィッシャ/
survey:<名詞>として「調査」。/サァーヴェイ/
p.53
– Part 2 /
防災について気になったエディ
[ what の用法 ]
[KS-12] Tell me what …
続けての間接疑問文は what の場合。where, when, how は副詞だった。
「何を見てきたの?(現在完了形)」
・Tell me what you have watched.(目的節)
what 以下「何を見てきた」は普通文。疑問文にはならない。
ちなみに余談だけど、what は疑問(代名)詞で名詞になる。名詞として使えるのは主語か目的語。
と言うことで、疑問文ではないけど主語としても使える。
「見てきたのはアニメ」
・ What I have watched is animation.(主語節)
使い方としては難しいかもしれない。
done (<= do):<動詞><過去分詞>。”have done”で現在完了形「やった」。やって、今もその状態だと言いたい。
“did”だと、「やった」けど、今もその状態かどうかは聴き手には伝わらない。
prepare:<動詞>「準備する、用意する」。
emergency:<名詞> 「非常」「緊急」「エマージェンシー」。
kit:<名詞> 「(ある用途向けの)装備や装置、キット」。
link:<名詞> ここではネット上の「URLリンク」を言っていると思われる。”hyperlink”の省略形。
hasn’t (<= has not):完了形+否定の短縮表記。完了形(have+過去分詞)”have”は<助動詞>として扱うので、否定形も<助動詞>ように後ろに”not”を置く。
recommend(ed):<動詞>「すすめる、推奨する」。
earthquake:<名詞> 「地震」。
Unit.4 – Read and Think 1
p.54
ここからリードアンドシンクのNewWordsには日本語訳が併記されている。一方で本文は長いのでそっちの解説を中心にやっていこう。
特にここでは分詞。先に 57ページの文法解説を先に読んでおいて欲しい。
過去分詞とは?現在分詞とは?
a movie called Live Your Dream:「映画/呼ばれている/リブユアドリームと」:「リブユアドリームと言う映画」。
名詞 movie の後ろに called 「呼ばれている」という過去分詞を置いて、受け身の説明を後ろから加えている。
The woman smilimg …:「その女性/微笑んでいる」:「微笑んでいるその女性」。
名詞 woman の後ろに smiling 「微笑んでいる」という現在分詞を置いて、能動体の説明を後ろから加えている。
She became attracted to Japan:「彼女は/なった/魅力された(状態に)/日本に対して」。
get tired とかと同じ構文。動詞 + 形容詞(過去分詞)。
thanks to …:<副詞句>「〜のおかげで」。副詞句なので、文末に置いている。直前の foreign culture が主語で thanks が動詞ではない。
p.55
教科書に「コツ」として書いてあるが、こういうレポートとか物語とかを読む時に大事なことのひとつは時系列の把握。
いつどこで誰の話(行動)なのかをちゃんと把握しつつ読む練習が必要。
線を引いたり、丸をつけたりして物語の流れを頭に入れていく。高校入試の試験でもとても役に立つ読み方。
ディスコース(discourse)は「論文」とか「会話」という意味。それのマーカー(marker)「目印」と言う意味。
文章の流れの目印となるもので、段落の先頭に書くことが多い。
「それから」「その後」「その後すぐに」「その後毎年」など。
both in A and in B:「Aの状態でもBの状態でも」。both A and B と習うが、AやBは名詞以外でもいい。
Unit.4 – Read and Think 2
p.56, p.57
– Read and Think 2 /
映画についてのレポート
[ 過去分詞 ]
[KS-13] a move called …
[ 現在分詞 ]
[KS-14] a woman smiling …
リードアンドシンクの文法テーマは[分詞]。
とても大事。
[分詞]とは<動詞>をもとに作られる<形容詞>のこと。
[過去分詞]とは、<動詞>+ed の形で受動態の意味で使う<形容詞>。
[現在分詞]とは、<動詞>+ing の形で能動態の意味で使う<形容詞>。
「えっと、<形容詞>ってなんだっけ?」
<名詞>を修飾するもの。
大事なことは、
英語では<形容詞句>を<名詞>の後ろにおいて後から付け足しで形容・説明できる
ということ。これが日本語にはないシステム。
例えば
「その映画館で上映している映画」
・a movie showing at the theater
日本語だと、「その映画館で上映している」が形容詞。「ある映画」が名詞。日本語はこの順番。
だけど英語は逆さま。「ある映画」->「その映画館で上映している」の順。
これが英語の難しさの原因。日本語にはない語順。
「あれ、そういえば確か<動詞>+ingは進行形で使ったような?」
です。あれはこの[現在分詞]。
過去分詞の例は、
「多くの人に見られている映画」
・a movie watched by a lot of peaple
同様に英語は「ある映画」「見られた/よって/人々の多く」の順番。
「あれ?それから<動詞>+ed は受動態で使った。」
です。あれはこの[過去分詞]。
もうひとつそういえば、[動名詞]も同じ形をしていた。
<動詞>+ing。
だけどあれは<名詞>。主語とか目的語で使う。
動名詞と現在分詞は同じ見た目なのでわかりずらい。
practice
(1) make => made
(2) hold => held
practice
(1) stand => standing
(2) wear => wearing
Unit.4 – Unit Activity
p.58
防災への取り組みを発表しよう
Real Life English(Speaking)
p.59
街中での手助け
That’s very kind of you.:<節><文>「とてもご親切に」お礼の言葉。
<補語形容詞>の”kind”の後ろに意味上の主語を示すとき、間に”of”を置く。”kind”なのは”you”。
“That’s very kind of you to do so.” 直訳は「あなたがそうしてくれるのは、とても親切なことです。」
“It’s very kind of you to ask.”「聞いてくれてよかった」
would like A to B:<句> 「A(人)にB…をしていただきたい」。
丁寧に話したい聞きたいときにこの表現をつかう。肯定文でも疑問文でも否定文でも使う。
“I would like you to help me.” 「(あなたに)手伝っていただきたいです。」
ちなみに疑問文は
“Would I like you to help me?” ではない。
文法的には正しいが、「私はあなたに手伝っていただきたいだろうか?」と自問自答になってしまう。
“Would you help me?” 「手伝ってもらえますか?」でいい。
逆に「(私が)手伝いましょうか?」なら、
“Would you like me to help?” と言える。
Learning Art in English (美術)
p.60
以上、第35回『ニューホライズン3』ユニット4
関連図書:

ワーク&テスト ニューホライズン 3年
引用元:

東京書籍 令和7年4月新刊 中学教科書 NEW HORIZON English Course 3 [教番:英語002-92]
東京書籍 発行