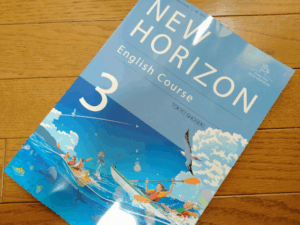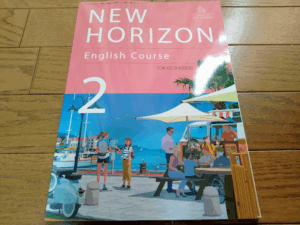第29回 中2ユニット7:P89- P99『ニューホライズン2』単語, 文法ガイド
『New Horizon』シリーズ 目次
2021年度令和3年度版(2ページ目)
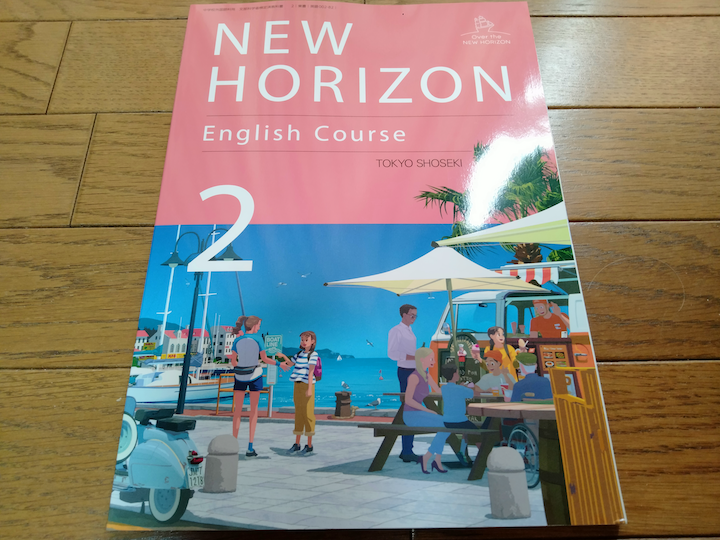
(DEEY─)ユニット6が終わっていよいよ中2の文法は最後の受動態、受け身表現。
中学教科書『ニューホライズン』の単語・用語解説シリーズ。
中2ラス前の第29回は─、 中学2年『New Horizon 2』の文法は完結編、
・ユニット7
・89ページから99ページまで
を解説します。
前書き、使い方
新単語は以下のような”凡例(ルール)”にしたがって記述しています。
─ 凡例 ─
word(s):<品詞> 「和訳」 。〜説明〜
phrase:<句>「和訳」。〜説明〜
英語は同じ綴りで<動詞>で使ったり<形容詞>で使われたりします。そのためここでは”どの<品詞>”で使われているかも併記します。
“<名詞>として(使われている)。”
と書かれていた場合は、その単語はいくつかの品詞の種類があるけれど、本文では<名詞>として使われていることを示します。
“<名詞>”
とだけ書かれている場合は、その単語はほとんどの場合<名詞>以外の用法はないことを示します。
『ニューホライズン 2』
─ 2025年度版 目次 ─
p.89
Unit.7 – What are World Heritage sites and their problems?
P.94
Unit.7 – Unit Activity
Grammar 6 – 受け身
p.99
Unit 7 – What are World Heritage sites and their problems?
p.89
中2最後の文法は受け身。「〜された」。
「その映画はその年の最高作品に選ばれた」
「その映画は多くの人に見られた」
「その映画はYouTubeでも見られる」
などの表現をどうやって英語で言うか。
p.90
– Part 1 /
世界遺産についての本
[受け身]
[KS-24] … is selected …
パート1でまずその受け身の作り方から。
「彼らはその映画をその年最高作品に選んだ。」
・They selected this film as the best film of the year.(元の文)
「その映画はその年の最高作品に選ばれた。」
・The film was selected as the best film of the year.(受け身)
動詞は be動詞 を使う。後ろに<動詞 +ed>と変形した形容詞を使う。
このやり方、意味は全然違うけど進行形に似てる。あのときは be動詞 + <動詞 + ing >だった。
あと、ここでは特に誰に選ばれたかは重要ではないので they は省略している。
select(ed):<動詞>「(慎重にいいものを)選ぶ、セレクトする」。
select as A:「Aとして選ぶ」
heritage :<名詞>「遺産」
site(s) :<名詞>「(建物を建てるための)敷地や用地」。
ウエブサイトのサイトもここから派生した意味。
natural:<形容詞>「自然の」
cultural:<形容詞>「文化の」
mixed:<形容詞>「合わせた」
selection:<名詞>「選択、選定、セレクション」。
“select” の名詞形。
standard(s):<名詞> 「標準、基準、スタンダード」。
発音は /スタンダード/。
decide(d):<動詞>「決める」。
過去形と過去分詞は同じ形。
UNESCO:<固有名詞> 「ユネスコ」「国際連合教育科学文化機関」。
名前は聞いたことがあるかもしれない。
general:<形容詞>「全体的な」「一般的な」
conference:<名詞>「カンファレンス」。
「会議」なのだけど、より公式的で専門的、何日かに渡って開催されるような規模のものも。
p.91
– Part 2 /
南アフリカに戻ったエディ
[受け身の疑問文]
[KS-25] Is … called …
パート2では疑問文の作り方。これは現在進行形の疑問文と同じルール。
「その映画はベストムービーに選ばれた?」
・Was the movie selected as the best movie?
fantastic:<形容詞>「素晴らしい」
hometown:<名詞>「地元、故郷、ホームタウン」
floral:<形容詞>「花の」
region:<名詞>「地域、地区」
known ( <= know )
plant:<名詞>「植物」
diversity:<名詞>「多様性、ダイバーシティ」
species:<名詞>「種」。
Unit.7 – Read and Think 1
p.92, p.93
– Read and Think 1 /
インドのタージ・マハールについて
[byつきの受け身]
[KS-26] … is loved by …
ここまでは受け身表現でありつつ「誰によってなされたか」は無関心にしていた。
それは一般人かもしれないし、あまり重要ではなかったこともあるし。
もし誰がそうしたかの情報を加えたいのならどうするか?例文で見ていこう。
「その映画は多くの人に見られた。」
・That film was viewed by a lot of people.
と[by + 行為者]を後ろに付加する。
さて本文だが by(誰によってなされたか)を明示する場合の表現が多く出てくる。
特に主語が人ではない場合、確かに[受け身]の表現は使いやすい。
ここでは “Taj Mahal” が主語の文が多く、したがって “It” や “Its” などの”無生物”<代名詞>が多用されていて読みづらいかもしれない。
built (<= build):<動詞>「建てる」の過去分詞。
emperor <名詞>「皇帝」
in memory of … <副詞句>「記憶の中で(として)/〜の」
wife:<名詞>「妻」
architecture:<名詞>「建築様式、方式、アーキテクチャ」
cover(ed):<動詞>「覆う、カバーする」
marble:<名詞>「大理石」「小さい色付ガラス玉、マーブル」
jewel(s):<名詞>「宝石」
material(s):<名詞>「材料、マテリアル」
from far away:<副詞>「〜から/遠く/離れた/」。
前置詞->副詞->副詞(形容詞)という変な並び。
because of … :<副詞句>「〜のため、が理由で」
pollution:<名詞>「汚染」
government:<名詞>「政府」
protect:<動詞>「守る、プロテクトする」
p.94, p.95
– Read and Think 2 /
富士山について
[助動詞つきの受け身]
[KS-27] … will be enjoyed …
受け身最後は、助動詞の can や will などと合わせて使う文。
「その映画はYouTubeでも見られる/(れるだろう)。」
・The film can ( will ) be watched on YouTube.
日本語だと「見れる」とも表現するが意味は受け身の「見られる」。
list(ed):<動詞>「〜のリストを作る」「リストに含む」。
seen ( <= see )
more and more:<副詞>「もっと/そして/もっと」
tourist(s):<名詞>「旅行者、ツーリスト」
climb:<動詞>「登る、上がる」
sunrise:<名詞>「日の出」
cloud(s):<名詞>「雲」。雲が数えられるのは不思議。
crater:<名詞>「火口」「隕石によるクレーター」
amount:<名詞>「(数・サイズ・価値などの)総量」
a … amount of … <形容詞句>「〜の〜な量」。
a large amount of …「膨大な/量/〜の」
trail(s):<名詞>:「(人やものが通ってつけた)跡」「トレイル」
recently:<副詞>「最近は」
take your garbage home:「持っていく/あなたのゴミを/家に」
cleanup:<名詞>「一掃、クリーンアップ」
campaign(s):<名詞>「(組織化された活動)、キャンペーン」
forever:<副詞>「永遠に」
Unit.7 – Unit Activity
P.96
日本の世界遺産の特徴を紹介しよう
Real Life English ( Speaking )
P.97
買い物 ─申し出る・要望を伝える─
goods:<名詞> 複数形で「商品」「グッズ」
size:<名詞> 「サイズ」
price:<名詞> 「値段」「プライス」
medium:<名詞> 「ミディアム」「真ん中」。
ここでは服のサイズの話をしているけど、マスメディアの「メディア」もこれ。パソコンとかの記憶メディアの「メディア」もこれ。
「媒体」と訳される。放送媒体、記録媒体など。
customer:<名詞> 「顧客」「商品の購入者」
How much …?:<句> 「いくらですか?」と聞くときの決まり文句。
How about this one? は、How do you think (feel) about this one? を略している感じ。「これどう(考える/思う)?」
I’ll take it/this/that. もよく使う。「それ/これ/あれにします。」という意味で、いくつかから迷って選ぶときに言う。メニュー見ながら迷って決めた時とかも。
GRAMMAR 6 – 受け身
P.98
>>> 受け身 〜視点を変えて情報を伝えよう〜
日本の世界遺産の特徴を紹介しよう
英語の歌 3
P.99
『Bad Day』
以上、第29回『ニューホライズン 2』ユニット7
関連図書:

ワーク&テスト ニューホライズン 2年
引用元:

東京書籍 令和7年4月新刊 中学教科書 NEW HORIZON English Course 2 [教番:英語002-82]
東京書籍 発行