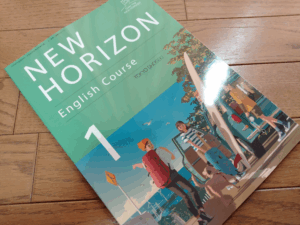2024年度『共通テスト英語』:実際に解いてなぜ時間が足りないかを考える
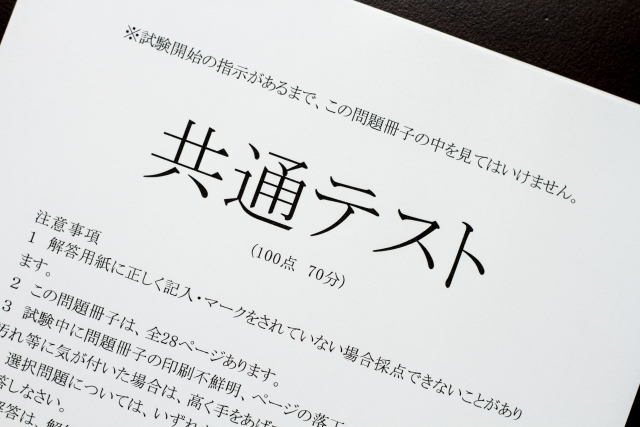
(DEEY─)今回は大学受験生に向けた話をちょっと。あるいは─
「大学入試『共通テスト』が”難しい”って聞くけど、どうなってるの?」
くらいに興味のある人向け。
2024年度(令和6年度)の『共通テスト』英語を実際に時間を計って解いてみました。
リスニング30分、リーディング80分。合わせるとTOEICと同じくらい?(長い!)
そしてTOEIC800点人間の目線で感想を。さらっと書こうと思ったが、めちゃくちゃ長い記事になってしまった。
なので目次をつくった。
(2025年12月19日)令和7年度(2026年度)の試作問題を解いた感想は以下から。
令和7年度『共通テスト 英語』試作問題を解いてみたので、個人的な感想など
2024年度『共通テスト』英語、実際に解いてみたけれど。
– 目次 –
1. 高校入試問題もすでに長文化
2. 「時間が足りない!」という声
3. 実際に解いてみた感想
4. リスニング [前半] 1, 2, 3
5. リスニング [後半] 4, 5, 6
6. リーディング [前半] 1, 2, 3
7. リーディング [後半] 4, 5, 6
8. まとめと速読について
9. 自分のWPMは測っておく
1. 高校入試問題もすでに長文化している
少し前に
2022年(令和4年度)の都立入試英語問題を解いた感想。英作文のコツなど
ということで、都立高校一般入試の英語問題を解いてみたことがある。感想は
「こんなんだったっけ?文字数すごい多くない?」
だった。解答時間はは40分。いつものように初見、事前情報なし、過去問未経験、
という条件ではあったけど─
30分かかった。もちろん100点は取れなかった。
ちなみにこの「一般入試問題」は、都立の中上位高校までが採用している共通問題で、
トップの日比谷高校から戸山・新宿あたりまでの上位校は、いわゆる”自作校”と呼ばれ独自に作成したの英語問題になる。
こっちは更に文字数が多い。高校入試で今やこのレベルですか。
2. 気になる「時間が足りない!」ということば
自分はこんな感じのブログを書いているので、ネット上で
「共通テストの英語が難化」とか
「共通テスト英語、時間足らない」
とか、妙によく目にする気がした。とくに今年。
まあでもこう言った、
「高校入試が長文化している」
「大学入試テストの難化」
という声は
「TOEICがどんどん難しくなってる」
と同じ文脈で語ることができるので、まあ納得ではある。なんで納得したかは
公式問題集やテスト精選模試など。やらないともう圧倒的に不利な時代だと納得
でも書いたけど、要はみんなきっちり対策するようになったから。
昔から赤本、過去問でみんな必死なのは確かに変わらないけど、ネットによる情報力は対策の精度とレベルを大幅に向上させてる。
しかも人生の懸かる受験。TOEICと違ってみんな一生に一度だから必死度が違いすぎる。万全の対策を打ってくる。なので
「もう、問題難しくするしかないじゃん?」
という流れ。正確に言えば、難しさは”若干増し”で、分量が”増し増し”という傾向。
TOEIC受けて、高校受験問題解いて、今回共通テスト解いて、みんなベクトルは同じ。
でもこの方向だと日本人の英語力はあんまり上がらない。実際世界レベルでの日本の英語力(発信力)は下から数えてすぐに現れる順位。
今回はまあいいか、そこは…
3. 結果。そして平均点、段階表示
さて『共通テスト』はネット上で問題も解答も入手できる。解説はないけど。
リスニング音声も聞くことができる。
今回リスニングはここからのmp3を再生しながら、別画面で問題を見ながら、紙に答えを書く。
リーディングも、同様に問題pdfをPCで見ながら、手元の紙に答えを書いていく。
とうい方法。
初見。過去問や模擬経験なし。むかし共通一次時代に経験あり。
という状況で解いてみた。結果は─
・リスニング:80点
・リーディング:74点
(90分かけて:84点)
2024年度の平均点と段階表示を調べると─
[平均点]
・リスニング:67.24点
・リーディング:51.54点
[段階表示:9段階(上位4%)]
・リスニング:93点
・リーディング:87点
[段階表示:8段階(上位11%)]
・リスニング:89点
・リーディング:78点
リスニングはまあいいとして、リーディングは噂通りの物量だった。
ひとつ言い訳。
普通はリスニングではメモしながら、リーディングでは記しどなをつけながら解いていくが、今回は画面見ながらだからそれができなかった。
4. リスニング [30分] 前半の感想 [大問1/2/3]
では、リスニングから感想を。
全体としては、[大問1]からすでに簡単ではないけど、[大問6]が難しいかというと、そうでもないかな、という印象。
ここからは80点取りたい目線で話します。
[大問1] – [A] :音声2回
[大問1]と[大問2]は2回再生されるし、ゆっくりだし。と考えているとちょっとやられるかも。
聴き終わって即答できるタイプではない。選択肢は言い換え(つまりどういうこと?)や、「そうは言ってない」系で一捻りある。
きちっと脳内に絵が描けて、その絵を保持したまま選択肢と照らし合わせる感じ。
[大問1] – [B] :音声2回
音声説明の内容に合致する絵を選ぶ問題。まあこれは易しめに入るだろう。だが、やっぱり「要はどういう状況?」みたいな感じで、一拍考える。
[大問2] – [B] :音声2回
今度は、音声が会話になってる。あとは同じように、「要はどういう状況?」という絵を選ぶ問題。
まあこれもやさしめに入るんだろう。
[大問3] 音声1回
ここから音声は1回のみ。
対話音声から内容の正しいものを選ぶ。これはTOEICまま。ただ問題文頭に状況が日本語で説明してある。これによってだいぶ易しくなる。
こう言った短い対話リスニングでは状況把握が一番神経を集中させるところだから。また説明文が日本語というのが面白い。
受験英語を解いていて思うのは、こうやって問題文や説明文が所々で日本語なこと。
これはこれで日本語脳と英語脳を行ったり来たりする脳力が必要なんだけど。
ここも難しくはないと思った。
以上が前半部分。
ここまでで、17問で配点は59点ある。思ったより配分は大きいと思った。
今後の状況によっては(得点に差がつかないとか)、この前半部分の配点は低くなるのかな?
80点が目標なら前半の間違いは、あってもひとつとかふたつだと思う。
というか因果が逆で、80点取れる人なら前半はほとんど取りこぼさないだろう。それが簡単だとは思わないけど。
問題文を先読みできる速読力と、リスニング中に脳内に絵が描ける能力があるということは、そういうことだろう。
前半で3つ4つを超えて間違っている場合は後半苦しくなると思う。
まずはリスニングの時間を増やそう。頭の中に絵を描く練習。頭の中に絵を描く順番は、日本語とは異なることに気づくのがコツ。
英語の語順で場面を描いていく。難しいんだけど。言うのは簡単だ。
5. リスニング [30分] 後半の感想 [大問4/5/6]
後半。
配点は引き算すると41点ということになる。
[大問4] -[A] :音声1回
一つは絵を見ながら今日の出来事を聞いて、時系列に並べ換える問題。
二つめは時間割を見ながら空欄を埋めて、スケジュールを完成させる問題。
ここで試されるのは「話を聴きながらメモできますか?」という能力。
大問4はそれの短文でやさしい版。
前半の[問18] から[問21]の時系列並べ替えは、4つ全部正解で4点。
後半のスケジュールを埋める[問22] から[問25]は、各1点の配点。
頑張って解いた割には配点が低い!
でもここは点数差がつくところだと感じた。8割取れる実力者ならここは全問正解の8点。
80点目標でも、リズム崩したりすると1点2点、なんてこともありそう。
[大問4] -[B] :音声1回
[B] もメモ取りながら、って感じ。
音声の前に状況把握と準備のために数十秒の時間が与えられるので助かる。
「聴きながら丸バツをつけていくのかな?」みたいな予測を立てれれば。
少し状況把握に時間かかる問題なので、初見なのか過去問で似たようなのをやったことがあるか、で結果は少し変わりそう。
もちろん経験者有利。でもこれだけ聴いて配点は4点。
[大問5] :音声1回
今回のリスニングでは一番難しいと感じた。
そのためか音声前の準備時間がかなりある。自分はこの時
「あれ?mp3が止まってしまったのか?いや大丈夫か。えっと、なんだっけ…」
などとやって無駄な時間を過ごした。経験がないとこういうところでも慌てる。
さてこの[大問5]では─「英語独特のメモの取り方を知ってるか?」なんかも鍵となりそう。
ニュースの見出しなどもそうだけど、
・be動詞は省略する
・そのため、beに続く現在分詞や過去分詞が後置修飾っぽく(名詞後ろ)的に使われる
・一般動詞はそのまま。三人称単数sもそのまま
などなどメモの取り方はルールを含めて練習した方がいい。
まあでも[問28]〜[問31]で、4問全問正解してわずか4点。気にしなくてもいいかも。
それから、[問32]の内容一致も設問文が長くて難しい(ぱっと見)。
[問33] なども、図の棒グラフやテキストを比較しながら、3つの国名見ながら、聴きながらだから難しい。
[大問6] :音声1回
最後は2人以上の会話文が2セット。
大問5に比べれば易しめなのかな、と感じたけど会話文は経験的な慣れ不慣れもあるので、人によるのかもしれない。
こういう複数人が出てきて「あーでもない、こーでもない」「わいわい」「じゃあ、そうしよう」
[問題]:”さて、結局どうなりましたか?”
は、難しいかもしれない。
こういった会話リズムに特化した練習は必要だと思うけど、米ドラマは難しすぎるし時間ないしそこまでやる必要もない。
この点ではNHKのラジオ英会話で経験を積むのは、もしかするとちょうどいいかもしれない。
配点は[A]が2問で6点、[B]が2問で8点だから、ここを取れる取れないは大きいだろうな、と思う。
ということでリスニング後半のテーマは、メモを取りながら聴いて理解する能力。
この練習は過去問とか模試とかでやるしかないんだろうな。特に資料を見ながら、という練習は。
TOEICにもこのような問題はあったと思う。英検にはあったかな?わからない。記憶にない。
でも後半問われるのは「メモを取る余裕がありますか?」ということだから、やっぱり英語力の問題になるんだろう。
6. リーディング [80分] 前半の感想 [大問1/2/3]
さてリーディング。
しんどかった。
TOEICの75分でも、けっこう体力持ってかれて当日午後は抜け殻になる。リーディングは基本的には、
1、状況説明文読む
2、問題文を全部読む(設問は読まない)
3、本文を一気に読む
4、問題を解く
でやってみた。これでどれくらい時間が足りないのか(余るのか)知りたかった。
本文を読みながら、順に問題を解いていく方法は採らなかった。
以下、振り返りながら”どうやって時間短縮するか”を考える。
[大問1] -[A]:(配点4)
インターナショナルデーのチラシの話。状況説明だけは必ず最初に読んでおく。
[問題1]は問題文だけ読む。「ただにするためには」と言ってるので、設問は読まない。
[問題2]は設問も少し読むけど「何ができるか?」なので本文をちゃんと読む。
[大問1] -[B]:(配点6)
日帰り遠足の話。こっちは問題先読みしてもどこまで効率的かは微妙だと思った。
記憶力勝負の問題。
というのも問題を順に解きながら、それに沿って本文を上から読んでいく流れ─ではない。
[問題3]”そこには何があるか?”
[問題4]”3つに共通すること”
[問題5]”どれが一番最近の建物か?”
どれも全部ちゃんと読まないとわからない。その上で記憶勝負。本文と設問を結構行ったり来たりした。
[大問2] -[A]:(配点10)
戦略ゲームクラブの話。本文はほぼ箇条書き。
本文読んでから問題を見ても本文の箇条書き数が多くて覚えてない。どこに正解があるのか行ったり来たり。
かと言って本文を読まずに問題文を読みながら、該当する本文箇条書き箇所を探し出す─
これだと何回も本文を読む羽目になる。下手すると問題の数だけ本文を斜め読みしてしまう結果に。
最初の問題[問6]の答えは最終行にある。
[問7]は、クラブアクティビティの6つを読んでから選ぶ。
[問8]は、コメント6つを読めばいい。
[問9]は、もう一回両方とも読む?読まなくても覚えている?
言ったり来たりの情報処理(脳内メモリとCPUと検索プログラム)。
[大問2] -[B]:(配点10)
海外旅行保険のレビューのはなし。
[問11] ”どれが正しいか?”
=>全体の4/5まで読まないとわからない。
[問12] ”最安プランには何が含まれないか?”
=>全体の4/5読まないとわからない。
[問13] ”二言で言うとどういう会社なのか?”
=>最初の2/5段落まででわかる。
[問14] ”結局このレビューワーの態度は?”
ここも問題順と本文順は並んでいない。上から解いていくことはできなさそう。
[大問3] -[A]:(配点6)
日本でのフォトラリーの思い出を、イギリスに帰ってからアップしたブログの内容。
正攻法(いったん全文読む)で解く問題。
右枠内のルールも読まないと、左のブログでの内容が不明瞭になる。
[問16] つまりどう言う状況ですか?
[問17] 読んでスーザンに言葉をかけるとしたら?
これらは国語の問題。
[大問3] -[B]:(配点9)
去年のエングリッシュデーで行われた”バーチャルサイエンスツアー(南国編)”のレポート。
ここは一転、問題解きながら読み進めることのできるパターン。
以上が前半。
問題数としては 23/49だから、45%といったところ。配点もここまでで45点。
ただここまでで40分かかってると最後までは到達しない。かといって30分で解けるか?というとかなりの速読が必要だろう。
自分はゆっくり丁寧にやった感覚で、ここまで36分だった。ちなみにここまで2つ間違えた(21/23)。
7. リーディング [80分] 後半の感想 [大問4/5/6]
後半はいよいよ”長文”な読解になる。
[大問4] :(配点16)
要約的な問題。本文読みながら、2ページ目のまとめ要約を見ながら、3ページ目の問題を解く。
全部並行にやっていくイメージなんだろう。
だとすると3ページに渡って行ったり来たりするけど、本文の読み込みは合計で1回で済ませたい。
それはちょっと難しいか。
[問25]は、最後まで読まないと無理っぽいか。
自分は13分かかった。ここまでで49分経過。
[大問5] :(配点15)
物語文。登場人物3人、それぞれの現況と原因となる過去の話が入り乱れる。
物語としては普通に読める。要約の部分は先に目は通しておくけど、本文は一気読み。
時系列とマキの言動に注意しながら。問題もそこまで難しくはない感じ。
と思ったが、時間を調べると18分もやってた。ここまでで67分。残り13分。
[大問6] -[A]:(配点12)
[大問5]まで全問正解すると76点。9割正解なら68点。
[大問6]の配点は合計で24点。
と言うことは、80点以上目標なら実質ここからが勝負。ここを全問正解で合計88点。
だけど、[大問6]-[A]まで解き切った人は少ないのではないだろうか?
自分もここで残り13分だった。明らかに急がなければならないプレッシャーのなかで解いた。
結果、13分では最後まで解けなかった。
[大問6]は、時間認識は条件によって相対的であると言う話。
ある程度どこかで聞いたことあったり、でも勘違いして理解していたり、という事前知識がかえって邪魔する可能性のある文。
だけどこの問題、後から見返すと結果論だけど本文全部読まなくてもいけるパターン。
ここへ来てそのパターン!
[問39][問40]:段落にふさわしい見出しは?
[問41]:要約箇所(your notes)で”問い”に繋がる前の文が”… speeds up … but a [41]”なので、答えは少なくとも”… slow down” じゃない?で、(1)か(3)になる。
[問42][問43]は、これは後出しジャンケンっぽいけど、本文に
“… retrospective timing, which is …”
“… perspective timing. It is … “
と、直後に丁寧に意味を書いていてくれる。それら定義に従うと選択肢が浮かび上がる。
[大問6] -[B]:(配点12)
残り12点分。自分は時間切れで手付かず。チリペッパーとわさびの辛さの違いの話。
最後は[大問4]と同じパターン。本文ページと、まとめメモページと、問題文ページをペラペラめくりながらの並行作業。
この問題は本文まともに読まなければいけないので、10分では解けないかな。
[問48][問49]とかは、なんだか選択肢の文表現が子供っぽい。この2つは本文読まずに常識で解けそうな感じ。
そのまま10分延長戦として解いてみたが、[問48][問49]は間違えた。[大問6]は、10分では足りなかった。
8. まとめと速読方法について
リーディングについて、このテストが終わったあとYoutubeやWebで総評動画を見たりした。
そこで東大生やらTOEIC満点・英検一級の錚々たるメンツで90点台と知った。
まあ国語もそうだけど、英語も100点は取れない分野。
内容一致問題は設問が微妙だと作者と読者で解釈が分かれるパターン。
だけど彼らをして時間がギリギリ、というのは流石にやりすぎ感がある。
「リーディング、こうやれば時間内に最後まで解ける!」
というのは理屈としては言えるけど現実的には難しいだろう。
なにせ今回は90点取ると上位3パーセントだ。80点で上位10パーセントに入る。
そのために時間資源を英語のリーディングに大量注入するかどうかは他の教科とのバランスによるだろう。
この問題を80点目指して勉強するとか、トラウマでむしろ英語嫌いが生まれるレベルな気がして
そんな余計な心配をしてしまう。
まあでもそれが現実だし、10代の若い脳ならだいじょうぶなのかもしれない。
自分でも初見で70点は超えたということは、正攻法でも準備して臨めば普通の人でもなんとかなるんだろう。
ただ速読は必須。
「じゃあどうやったら早く読めますか?解けますか?」
気持ちは分かる。これについて詳しくは別の記事にしますけど。
まずは単語と文法はある程度身についている前提で話すと、共通テストはもはや国語の問題になってきているので
つまりは言語解釈と記憶力・情報処理能力の勝負になってきていて
「普段から日本語でも本を読んでますか?」
「国語は得意ですか?時間内に解けますか?」
という問題にもなってくる。
・設問を記憶に留めながら本文を読む能力。
・どこに何が書いてあったかを思い出せる能力。
・時系列に並べ替えれる脳内描写力。
テクニックとしてスキミングやスキャニングなど言われているけど、日本語で読むときはみんなやってる。
その能力は普段の読書や普段使っている語彙力が支えている。これは日々の訓練が必要で母国語でもみんな10年かけて磨いている部分。
そこを一年二年で何とかしようと言うのが受験なので効率的にやるしかない。
受験用の単語帳・熟語帳・過去問や対策本が必須になる。
そして一般用の単語帳などには手を出さないこと。
もう1つは、英語の綴りから日本語の綴りを経由しないでイメージが出てくること。
例えば dog と書いてあったら「犬」という字は思い浮かばずに「犬のイメージ」が出てくると思う。
特に動詞はイメージが定まらないことが多いと思う。
take, give, make, put, get, turn, set…
どんなイメージが出てくるだろうか?
とにかく日本語を経由しないこと。映像(経験)と繋げること。
文字と映像がリンクしてれば理解に秒かからない。脳内処理時間は全然違う。こういう単語をどれだけ増やせるか。
9. 自分のWPMは測っておく
2024年度の共通テスト英語の総語数は6,200語とのこと。
これを80分で解くには、49問の解答時間を半分と仮定すると40分で読むことになる。
・6200/40 = 155 文字/分(WPM)
(”WPM” は Word Per Minutes で1分あたりの語数)
このスピードはTOEICのリーディングで最後まで読み切れる速度と同じ。
TOEICのリーディングも150WPMが必要と言われている。だから相当早い。
ちなみに共通テストのリスニングの音声スピードも同様に150WPMくらい。
単語も文法も易しく文も短ければ150は行けそうな感じがするかもしれない。
ちなみにネイティブは200 – 250 WPM。レベルが違う。
(2024年12月)

共通テスト過去問研究 英語 リーディング/リスニング (2026年版共通テスト赤本シリーズ)

2026-大学入学共通テスト 実戦問題集 英語リーディング (駿台大学入試完全対策シリーズ)