公式問題集や模試:やらないともう圧倒的に不利な時代「TOEICを受験した」第5回
TOEIC対策として利用した:CNNイングリッシュエクスプレス『TOEICを受験』第4回
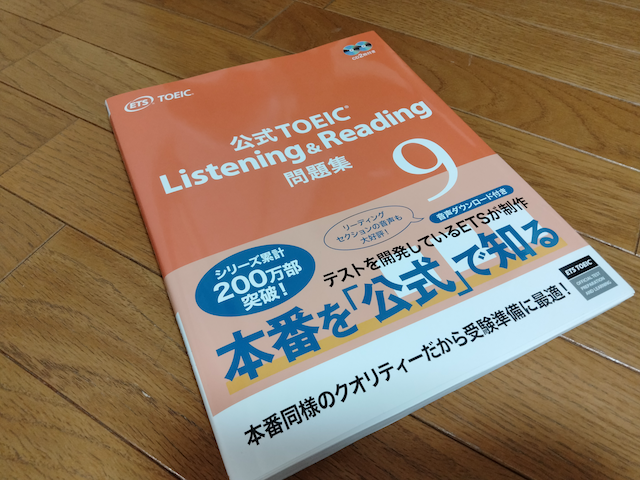
(DEEY─)先日の3回目のTOIEC(LR)受験では、事前対策として模試問題集を2冊購入して臨みました。
・『公式TOEIC L&R 問題集 9』IIBC(国際ビジネスコミュニケーション)
・『TOEIC L&Rテスト精選模試』加藤優、B.Towle、P.McConnell
その1年半前の2回目はあえて「TOEICを全くの準備なしの初見で挑む」という縛りのもと受験し玉砕の570点。
比較のために先日の受験では準備のうえ挑みまして、今回はこれらTOEIC模試問題集のレビューをしようと思います。
結論としては受験するのであれば「買う」の一手で、むしろやらないと相当不利なのかなとういう感想。
1)TOEIC受験者数は大幅アップ
そのTOIECの受験者数、調べると自分が最初に受けた頃と比べると、すごい伸び。
1995年50万人、2000年100万人、コロナ前の2018年に266万人。
目的や理由は人それぞれでしょうけど、繰り返し受ける人も増えたのではないかと考えます。
公的証明も社会での認知度もあがり、高得点であることが確実に有利な世の中になったのでしょう。
インターネットの普及も後押したのでしょう。ネット、SNS、ブログ、DVD、ダウンロード、参考書・・・
そしてなんと「公式」から発売されるようになった問題集。
対策を十分に行う人、何回も受ける人。これらの結果として受験者の正解率はおそらくかなり上がったと想像します。
2)「TOEICって難しくなってるよね」
実は同じことが中高大の受験でも起きていると言われています。
現在の学生は私たちの頃と比べてはるかに難しい問題を解いていると。
そして同様にTOEICも問題を少しずつ難しくしていると憶測します。公式では
スコア基準は常に一定であり、英語能力に変化がない限りスコアも一定に保たれます。
[公式L&R問題集9] 5ページより
と書かれていて事実、毎回平均点は600点前後で推移しています。裏を返せば、もしその通りだとすれば
「日本人の実力は上がっていません」
ということになる。だけど、
・多くの受験者が公式問題集など「買ったこともない」状況
・ほとんどが模試などの「対策をしっかりやっている」状況
で平均スコアが同じ、と言うことは考えにくい。
事前に模試をやって対策をしている人が増えるほど、試験内容を難しくしなければ、平均点は上がってしまうはずです。
TOEIC Program DAA2022(和文)2022年8月版(pdf)
それでもほとんどの人が事前模試を実施するようになれば、どこかのタイミングでこの効果による平均点の上昇は止まるんでしょう。
その時平均点の上昇とは受験生の真の実力の上昇と等しくなる。もうすでにそうなっているかもしれません。
とにかく個人的体感でも明らかに難しいです。90年代に比べると。
それはさておき、そういうことなので本試験のテキストは持ち帰れない以上、模試や問題集をやらずに前回の記憶にだけ頼るのは完全に不利と言えます。
今回はなんとなく2冊買ってみました。基準はAmazonのおすすめ順。
3)公式TOEIC L&R 問題集 9
2022年10月19日発売の最新版で第9版。
・「リーディングセクションの音声も大好評!」
・「シリーズ累計200万部突破!」
と帯の吹き出しが申しております。税抜3,300円。CDが付属。ダウンロードもできますが会員登録が必要なのがひと手間。
手触りのよい紙質で物理的には最高です。
解答集が別冊となっており、簡易のりで留められているだけなので簡単に本体から分離します。
二回分の模試と解答。解答と解説は丁寧。
解答冊子にはリスニングだけではなく、リーディングの問題解答文も掲載しているので問題冊子と解答冊子を行ったり来たりする必要がない仕様。
ページ下部には[Words & Phrases]の一覧囲みと[Expressions]の説明囲みがあって、まとめて一覧できて整理・復習・暗記に便利です。
ただ一歩問題の解説等を離れてからの全体的な話─、例えば問題の傾向や各パートの説明やアドバイス─、といった類は皆無です。
何回も受けていたり事前に情報を得ている人にとっては「既知」ということで省いたのでしょう。
特に個人著者名は記されていません。この後で紹介する本と比べると、そこはあっさりですね。
本試験合わせのためか、本自体が変形のA4型で大きいのが好き嫌いあるかも。いや本番の冊子より横幅大きくないか?気のせいか?
4)TOEIC L&Rテスト精選模試
こちらも帯付き。
・「良問x丁寧な解説でスコアが上がる最強模試」
・「シリーズ30万部!」
・「1,980円」
帯の煽り文句に値段アイコンをつけるという価格アピール。
自分は上記2冊買って双方パラパラめくって、こっちの模試をやりました。
著者が加藤優さんというかたでTOEIC満点、TOEIC(SW)も満点という。問題の監修等共著にネイティブが二人。出版社もジャパンタイムズ社という信頼性。
そして持っている情報が皆無のため、全体的なコツやハウツー、アドバイスを読みたかった。
本も変形B5型で一回り小さく?扱いやすい。ダウンロードもシンプル簡単。余計な登録作業なし。
自宅だし集中力もないので、リスニングとリーディングは別日に実施。
実はここはちょっと大事だと思います。もし自らが「若くない」と自覚しておられるなら。
TOEICの試験はご存知の通りかなり集中力を使います。この集中力は人により年齢により異なると思いますが、疲労感が残るのは間違いないです。
模試とはいえ集中はしますので、本番までにメンタル的にも回復しておきたいところ。
さて結果は─
・リスニング(試験二ヶ月前):73/100
・リーディング(試験一ヶ月前):71/100
でした。模試後の感覚で「7割くらいできたかなー」で本当に7割。
ちなみにその後の本試験ではL410、R390。
この問題集は「少し難しい」とも捉えられるけれど、模試とその対策の効果があって本番の点数が伸びたのだから「実質同レベル程度」とも考えられる。
実際の本試験中に「なんか易しいな」という感想でもなかったですし。
5)TOEIC模試の効果効用
本試験では冊子を持ち帰れないので、試験後に結果を検討分析することができない。これでは対策が難しい状況ですね。モヤモヤが残るし。
英検のように公式から過去問を出せばいいのに、と思いますが『模試問題集』が出ているのであればほぼ同じことですね。
さて自分的に模試をやってよかったことは、受験生のそれと同じで何も目新しくはないですけど─
1)自分が完全に苦手なパートが存在することが認識できた。
対策できるかは別。能力的に問題があるから苦手な訳で、それを克服できるかは「むしろ」可能性は低い。
自分は、パート2が苦手。イギリス英語が苦手。パート8が苦手と判明。
2)リスニングの間の取り方がわかった。
具体的には、問題と次の問題のすき間で次の問題の設問を先読みして、内容の事前把握を試みる。そうできるテンポで設問を選ぶ。
3)リーディングの時間配分感覚がわかった。
それなりにテンポ良くいかないと最後まで辿り着けない。模試では10問残した。
繰り返しますが、できるかどうかは別なのが・・・
6)600点目標に模試問題集を活用
ここからは平均点600点を取るパターンとは?について少し考えたい。
TOEICは4択なので、1000点の1/4の250点は取れます。ですがそれはいったん抜きにしましょう。英語力のみで600点を取ることを考えます。
例えばリスニングはPART3までで、6+25+39 = 70問。そこまでの85%正解すれば、その後のPART4の30問がゼロでも約6割。
でも前半8割の正解率を叩き出せるなら、リスニングPart4がゼロはあり得ないですね。そしてリスニングは全員が最終問題まで到達しますね、当たり前ですが。
でも後半に行くほど難しいので、前半の正解率が鍵なのは確か。「問題が難しくなっていく直線」と「自分のリスニング力が落ちていく直線」の交わる点をどれだけ先延ばしできるか。
リーディングに関してはPART7のまでで、30+16+29 = 75問。うち80%正解すれば、その後の25問できなくても約6割。
あるいは全体の80%まで読んで、75%の正解率で6割。リーディングだとこの辺りが現実的でしょう。
うーん、でもやはり英語を勉強している人たちが受けている試験だと感じます。600点は結構ハードル高い。
7)模試問題集を活用
「このTOEIC模試問題集を丁寧にかつ何周かする」で何点まで取れるようになるのか?と言われたら・・・
結構取れると思います。「600?、700?」いけると思います。TOEICはそこまで難しい単語も文法も多くないですから。
そしてビジネス特化なので、そういう場面状況があり、ビジネス特有の単語や言い回しがあり、ということなので何回もやる意味は結構あると思います。
やっていく上でのポイントは、併記されている丁寧な日本語訳を活用することだと思います。
英文はネイティブなものですし、ビジネス英語や日常生活必需な実用英語ですし良い素材だと思います。
大事なことは「やり方」なのかな?と思っています。英訳をやりましょう。
ちなみに自分は普段専ら『CNNEE』をやっています。政治や事件、事故や裁判、宗教や人権などTOEICには関係ないですが。
ですが今回の模試問題集の解説や本文や紙質を見て触って「これもいいな」と思ったので記事としました。
けっきょく勉強は自分の気に入った本を使うのがいいのだと思います。手触り、製本の質、表紙の色使い、著者の言葉遣い・・・
開く気になる、復習する気になる、その前に手に取る気になる。
こういうのが意外と大切かなと。
(以上、2023年7月)
『TOEICを受験した』シリーズ続編:第6回
2023年の夏はS&Wチャレンジ:試験会場の雰囲気や内容『TOEICを受験』第6回

公式TOEIC Listening & Reading 問題集 10

TOEIC® L&Rテスト精選模試【総合】

