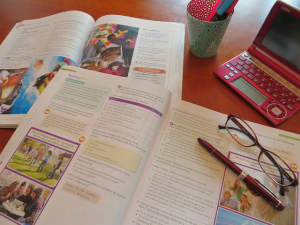マークピーターセン『日本人の英語』:シリーズ4冊は英語の思考ロジック解説書

(DEEY─)今回は岩波新書からのベストセラー。「著述できるほど日本語が堪能な英語ネイティブ」からの日本人英語学習者へのアドバイス集である─
『日本人の英語』シリーズ4冊
のレビューを中心にそのほか『岩波新書』ライブラリーからの英語関連の著書を一覧形式で紹介します。
特に当シリーズはスピーキングやライティングのアウトプットが必要になったときは必読レベルかなと感じます。
昨今ではユーチューブでもバイリンガルな方々が多々、英語学習者へ向けたコンテンツを発信しています。
個人的にはサイモンのイキれる英語教室が気に入っています。やはり英語ネイティブの日本語による英語論は面白い。
とは言いつつ当サイトの所々で書いていますが、個人的に「TOEIC800点くらいまでなら日本人に習った方が納得感が高いし効率的かも。」と思っています。
実はこの『日本人の英語シリーズ』でさえ、リーディングやリスニングを中心に学習している間は読んでいてあまり響きません。
刺さらないのです。他人ごとのようなエッセイを読み流す感じになって残らないのです。
でもアウトプットを始めるとあちこち刺さって、1日なんかではとても読みきれないという感想に変わる。
1)『日本人の英語』1988年
『岩波新書』からの刊行で初版は1988年。ですが、全然古くない。
「ネイティブ・スピーカーにとって「名詞に a をつける」という表現は無意味である。・・・(本書より)」
という見事な帯煽りで本書を手に取った人をレジへと誘うベストセラーの第一弾。
” ネイティブ・スピーカーにとって「名詞に a をつける」という表現は無意味である。
[日本人の英語:初版帯文言]
英語で話すとき— ものを書くときも、考えるときも— 先行して意味的カテゴリーを決めるのは名詞ではなく a の有無である。
もし「つける」で表現すれば、「 a に名詞をつける」としかいいようがない。”
内容はその冠詞に始まり単数・複数、前置詞、時制、関係詞、受動態、副詞、接続詞と一通りの文法を網羅します。
もとは雑誌『科学』の連載だそうで、それをまとめたもの。どうりで科学技術系の例文が多いわけです。
本文の文体はある意味「先生的な、上から目線的な」キレのある煽り気味の文章です。
1988年当時の人がどのような気持ちで読んでいたかは分からないですが、今読むと「けっこう煽るよねー」という感じ。
同時に日本語の難しさ英語との言語距離も実感されていて、2言語間の違いの説明に腐心している様子も滲み出ています。
でもこれだけの文章量をロジカルに日本語で書かれているというのは脱帽です。
ちなみに「単語は短い方が重要」的な法則がありますね。”a”はとても重要で意味のある単語と考えるべきなのでしょう。

日本人の英語 (岩波新書)
2)『続 日本人の英語』1990年
2年後の続編。目次を見ると内容は前回を踏襲している風ですが、日米映画の背景やセリフを引用していて、どちらかというとエッセイ風味となっています。
全体に占める英文の比率は1/3以下という感じでしょうか。
また著者の「日本語ってムズいよねー、俺大丈夫かな?」的な日本語論や自虐も散見されます。
勢い飛ばし読みになりがちなのですが、ところどころ刺さることが書いてあり急に立ち止まる感じでしょうか。
” the Japanese だろうが、Japanese people だろうが、日本語に訳したら、両方とも同じ「日本人」という表現になるのである。
[続 日本人の英語:初版帯文言]
しかし、英語では、この the の有無によって、表現にこめられた「日本人に対する態度」が全然違う。”
句点が多いですが原文ままです。

続 日本人の英語 (岩波新書)
3)『心にとどく英語』1999年
二作目からは7年後。著者のピーターセンさんは1作目出版時点ですでに明治大学の英語科の教師をやられていたようで、さらには時々アメリカでも日本語を教えていたようです。
本作は、これまでと同様映画からのセリフ、大学の生徒の英文、そしてアメリカの大学の生徒の日本語、筆者の身の回りの出来事─などをネタとした引き続きエッセイ風な作品。
前作よりは英語の割合は増えています。まだ自分も読んでいる途中です。
” ある日、大学生に ”She got into the classroom” を日本語に訳してもらった。
結果は、全員が「彼女は教室に入った」とした。
「それでは、”She went into the classroom”は?」と訊くと、皆同じく「彼女は教室に入った」にしたのだった。
つまり、どういうわけか、彼らには両方とも同じようにしか受け止められていない、という驚くべき事実を思い知らされたのである。
[心にとどく英語:初版帯文言]

心にとどく英語 (岩波新書 新赤版 604)
4)『実践 日本人の英語』2013年
4作目は今から10年前に出版されました。3作目からは14年後。
本作品は”実践”が示すとおりで、大学の生徒が書いた英文を著者が添削していきます。「私ならこうする」的に。
” ご注意!この英訳では「意味不明」!?
「昨日、私は自分のブラウスを買いに渋谷へ行きました」
-> Yesterday, I went to Shibuya to buy my blouse.「私はニューヨークで彼に会えました」
-> I could meet him in New York.簡単な日本語ほど、落とし穴がいっぱい!
[実践 日本人の英語:初版帯文言]
一つ一つのお題を一緒に解いていく、考えていく全220ページ。一気読みは勿体無い。じっくりと焦らず立ち止まりつつやっています。
どんくらいかかるだろう?一年くらい?そして終わったら二周目。

実践 日本人の英語 (岩波新書)
5)岩波新書の英語関連作品
岩波新書では英語に関連したものが定期的に発刊されています。「なぜ日本人は英語ができないのか?」論は昔からありました。
以下、英語・外国語関連の著書リストです。
・外国語の学び方:渡辺照宏(1962年)
・英語の構造(上):中島文雄(1980年)
・英語の構造(下):中島文雄(1980年)
・外国語上達法:千野栄一(1986年)
・英語の感覚(上):大津栄一郎(1993年)
・英語の感覚(下):大津栄一郎(1993年)
・日本人はなぜ英語ができないか:鈴木孝夫(1999年)
・伝わる英語表現法:長部三郎(2001年)
・日本人のための英語術:ピーター・フランクル(2001年)
・日本の英語教育:山田雄一郎(2005年)
・英文の読み方:行方 昭夫(2007年)
・外国語学習の科学:白井恭弘(2008年)
・英語で話すヒント:小松達也(2012年)
・英語学習は早いほど良いのか:バトラー後藤裕子(2015年)
・小学校英語のジレンマ:寺沢 拓敬(2020年)
・英語独習法:今井むつみ(2020年)
こういう古い本のリンクが消えずに残してあるアマゾンはありがたい。
(以上、2023年7月)